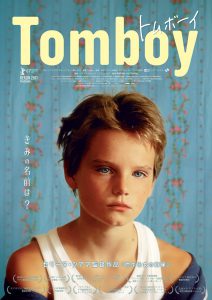男の子に“なりすます”イノセントなひと夏の物語『トムボーイ』 カンヌ受賞『燃ゆる女の肖像』C・シアマ監督初期作

セリーヌ・シアマ監督の長編デビュー2作目
『燃ゆる女の肖像』(2019年)で18世紀に生きる女性同士の深い愛情について描いたセリーヌ・シアマ監督が、2011年に長編デビュー2作目として撮った映画がこの『トムボーイ』。監督が長年暖めていた、女の子が男の子になりすます話です。

『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
主人公は、自らを“ミカエル”と名乗る10歳のロール。転勤が多い両親と共に、新しい土地へ夏休み期間に引っ越してきます。新居となる集合住宅には同じ学校に通うことになる子どもたちが何人か居て、遊びの輪に入れてもらうようになります。そして男の子として在りたいロールはミカエルとして、両親にそれを隠しながら友人たちと家の外で付き合っていきます。

『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
“男と女”という認識はありながら、まだ性的な部分も含めての恋愛感情を持ち合わせているかは微妙な年齢として「10歳」が描かれていて、女の子リザと2人で遊ぶようになってから、ミカエルに新しい気持ちが芽生え始めます。しかしそこは10歳なので、その「なりすます」ことに綻びが出てきます。

『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
家族と学校がほとんど世界の全てだった子ども時代
監督はインタビューで「子ども時代のアイデンティティの混乱について語ることはほとんどタブーのようだが、実際には強い刺激とある種の官能性を秘めた時期」と語っています。その言葉がストンと腑に落ちるくらいに、この映画での子どもたちのやりとりを見ているうちに、成長するにつれて段々と自認するようになるまで、自分もかつては未分化のセクシュアリティを持っていたな、と気づきました(ちなみに終盤には、誰しもそうなんじゃないかとも思えるほどになっていました)。

『トムボーイ』メイキング© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
話を戻すと、映画ではあまり思い出すことのなかった子どもの頃の記憶の引き出しが勝手に開くような、とても繊細だけど強烈なシーンが続きます。体格でジェンダーが分かりやすくなる前の本人の性別の捉え方への混乱と、子どもの無邪気さと暴虐性、そして親と子という関係の難しさが複雑に絡んで、物語は小さくも切実に回転していきます。子どもの頃に、家族と学校がほとんど世界の全てだったことが追体験できるような舞台のスケールのミニマムさもうまく機能して、ツーンと胸のあたりが痛みました。

『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
なかなか得難いイノセントな感触 ひと夏の通過儀礼
昔、予備校の先生が「“わかる”というのは、文法的に言うと“分ける”ことができるということ」だと動詞の活用形についての授業で言っていたのが、ずっと頭に残っています。「わかる」という言葉についての理解とともに、とてもいい言葉だなと思っていましたが、この映画では自分のアイデンティティについて“わかっていることとわかっていないこと”が同じくらい尊いものとして表現されていて、ハッとしつつ自省しました。

『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
また、滅多に得られないイノセントな感触に心を動かされました。言葉を知ると分別ができるようになって、さらに分けることは気持ち良かったりするので自分もついついアレはコレだよね、なんて語ってしまいますが、その“分ける行為”自体は大切なわけじゃなくない? と、社会に問いかけるような映画になっているなと思いました。

『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
ただ、その側面だけではなく、一人の人間ミカエルがある夏に経験する通過儀礼とも言えるような、大人になっていくまでの一つの経験をファンタジックに描いた、とてもかわいらしく、いい作品でした。
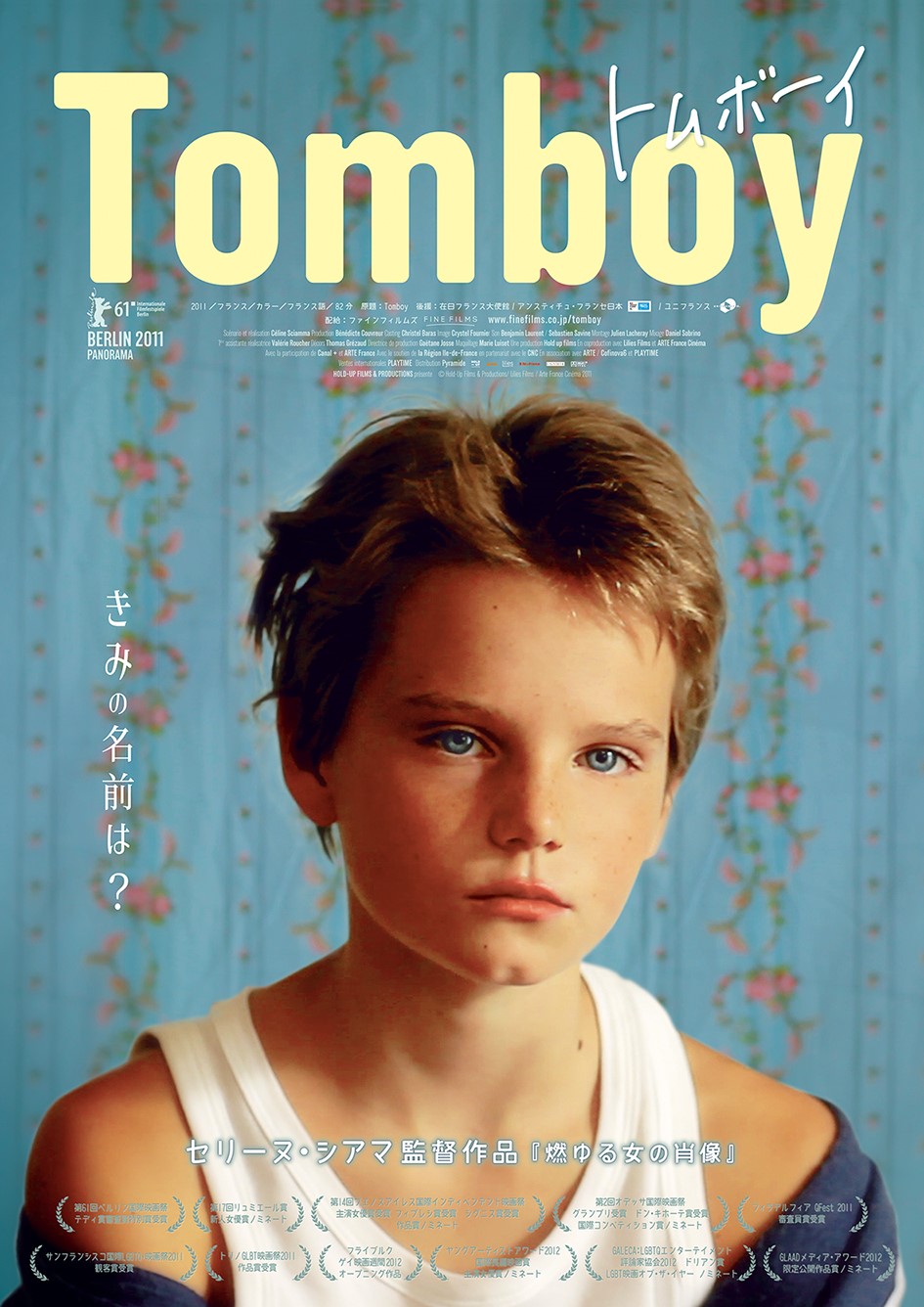
『トムボーイ』© Hold-Up Films & Productions/ Lilies Films / Arte France Cinéma 2011
文:川辺素(ミツメ)
『トムボーイ』は2021年9月17日(金)より新宿シネマカリテほか公開