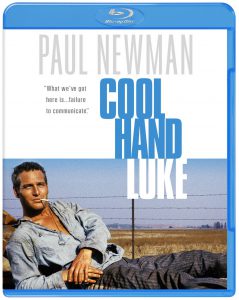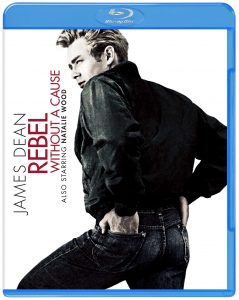暴力シーンの解禁は映画を進歩させたか? 規制コードが育んだ表象~『捜索者』『グッドフェローズ』から最新作『Mr.ノーバディ』まで

プロダクション・コード撤廃は映画を進歩させたか?
かつてのハリウッドの映画作りの基準となっていたプロダクション・コード(ヘイズ・コード)が公式に廃止されたのは1968年のこと。このコードにより、流血シーンや過度なバイオレンス・シーンは描いてはいけないとされていたから、西部劇で悪党が銃で撃たれても単に「うっ!」と呻いてバタンと倒れるだけという描写が、それまでは当たり前だった。
日本でもハリウッドのシステムを模範として映倫が作られていたから、古い時代の邦画だと時代劇で斬り合いのシーンがあっても同様に斬られた悪党はただ倒れるだけ。テレビだと今でも規制があるので血なまぐさいシーンというのは描かれない。
コードが廃止され、流血シーン、バイオレンス・シーンが直接描かれるようになった代わりに導入されたのが現行のレイティング・システムだが、果たして暴力シーンを直接描けるようになったことが映画の進歩に繫がっているのか? というのが今回のテーマだ。
名作『ある戦慄』と新作『Mr.ノーバディ』の決定的な違いとは
コロナ禍の昨今、新作映画の試写もオンラインで済ませてしまうことが多いのだが、久しぶりに東宝東和試写室で新作『Mr.ノーバディ』(2021年6月11日公開)を見てきたところ、抜群に面白かった。
同作の主人公は、あらゆる武器や格闘技に精通したアメリカ政府最強のエージェント、という過去を持つ男。現在は工場勤めのしがない家庭人になりきって生活していたが、ある事件をきっかけに最強の戦士として返り咲く……という設定そのものがまず面白いのだが、復活のきっかけとなる事件の描き方が実に今風で、胸のすく思いにさせられる。

『Mr.ノーバディ』© 2021 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. All Rights Reserved.
それは、たまたま乗り合わせたバスに、無法者の若者たち6~7人が乗り込んできてやりたい放題するのを阻止するべく、ジジイ呼ばわりされながらも持ち前のスキルを駆使して相手全員を叩きのめして病院送りにするシーン。設定としては、ニューヨーク郊外を走る地下鉄車両に乗り込んできたチンピラ二人組が乗り合わせた乗客たちを恐怖のどん底に引きずり込む、という名作『ある戦慄』(1967年)とほぼ同じだ。
『Mr.ノーバディ』が『ある戦慄』と決定的に違うのは、主人公が反撃して相手全員を叩きのめすシーンを、CGなどを駆使して流血や骨がへし折れる様子も含めて過度なバイオレンス・シーンとして描いていること。『ある戦慄』は前述のプロダクション・コード廃止の前年の作品で、描かれていたのはほぼ心理的な怖さだけだった。どちらの方がゾっとさせられるかといえば『ある戦慄』に軍配が上がるが、スカッとさせられるのはもちろん『Mr.ノーバディ』の方。どちらが優れているとは一概に言えない。

『Mr.ノーバディ』© 2021 UNIVERSAL STUDIOS and PERFECT UNIVERSE INVESTMENT INC. All Rights Reserved.
プロダクション・コード時代のハリウッド映画における暴力表象とは?
ポール・ニューマンの代表作『暴力脱獄』(1967年)は、そのタイトル(邦題)から受ける印象とは裏腹に、描かれる暴力シーンといえば囚人同士の素手での殴り合いのみ。ぶちのめされて鼻血を出すくらいの描写はあったと記憶しているが、今日的なバイオレンス映像を見慣れている人が見たら肩透かしを食らうに違いない。
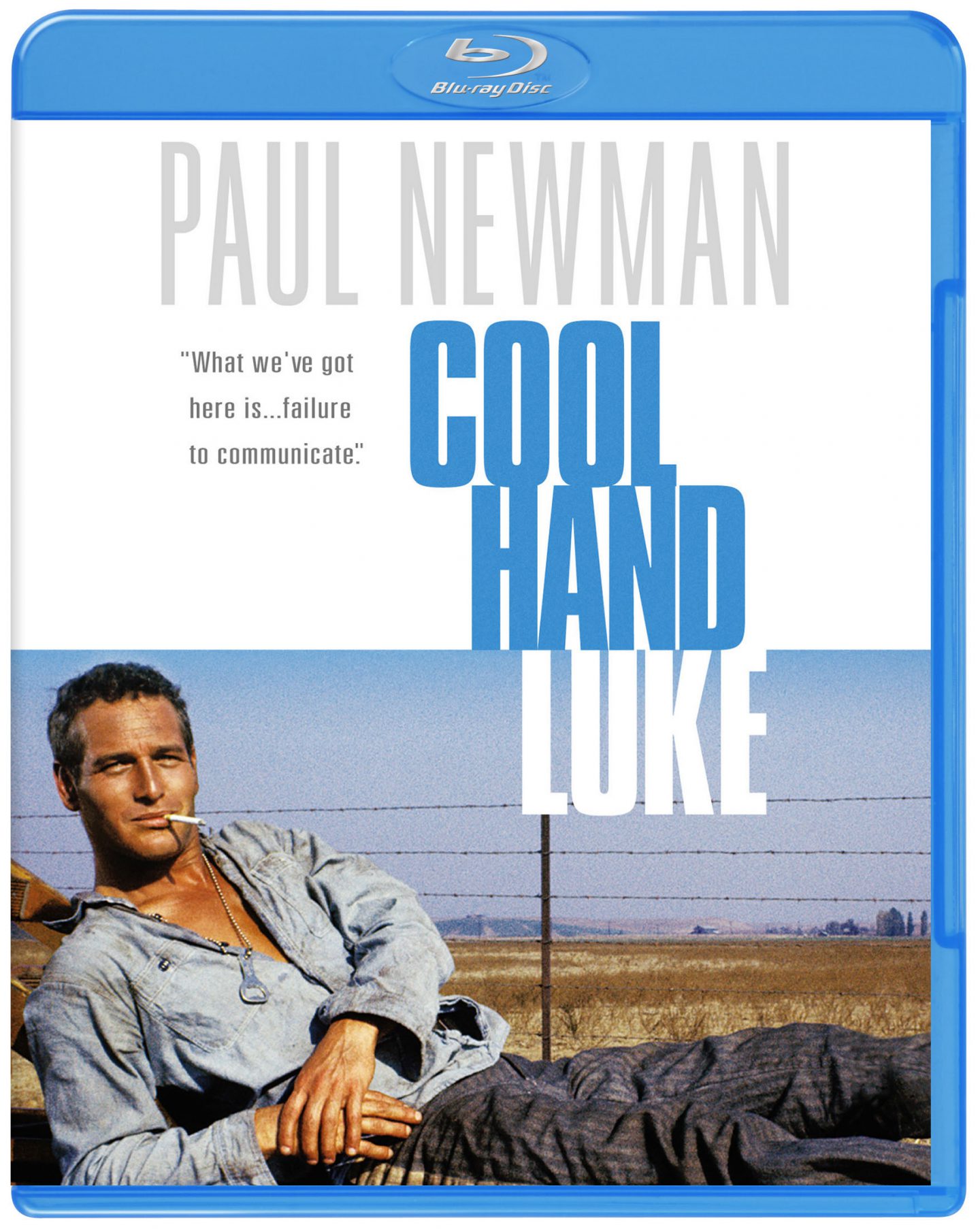
『暴力脱獄』デジタル配信中
ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD特別版 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
© 1967 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
だが、直接的な流血シーンがないと観客にゾッとするような怖さを感じさせることが出来ないのかというと、そんなことはない。ヒッチコックの名作『サイコ』(1960年)のシャワーでの惨殺シーンは当時の観客にショックを与えたが、実はナイフがジャネット・リーの身体に直接突き刺さるカットは皆無。
https://www.instagram.com/p/BYyU-26F1Ps/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ffdb71ba-e54f-4312-95d4-5094217f01ea
しかもコードによってヌードも禁止されていたから、シャワーを浴びていて殺されるというシーンであっても、乳房もヘアーも画面に映らないように綿密に計算されている。『サイコ』は、コードの枠内でいかに観客を怖がらせることができるかについての、ヒッチコックの挑戦状のような作品だった。
ジョン・フォードの名作西部劇『捜索者』(1956年)でも、主人公ジョン・ウェインが兄一家をインディアンに惨殺され、さらわれた姪っ子二人を救うために旅に出るというシチュエーション自体はかなり暴力的だ。しかし、残酷な場面はすべて台詞のやりとりで観客に想像させるに留めており、そのことが却って観客の想像力を刺激する。

『捜索者』デジタル配信中
DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
© 1956 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.
具体的には、惨劇の末に燃やされた廃墟となった兄の家に辿り着くと、慕っていた兄嫁の着ていたドレスが剥ぎ取られて捨てられている。焼け落ちた家屋の中には、裸にされレイプされた上で惨殺された死体が焼け焦げて転がっていることを想像せざるを得ないのだ。

『捜索者』© 1956 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.
追跡の旅の途中で、婚約者のいた年頃の姪っ子が同様に惨殺されていた現場を見つけた主人公は、遺体を自分の着ていたコートに包んで埋葬してから、旅の同行者である彼女の婚約者の許に戻る。その時は真実を話せないが、後になって彼がインディアンの一団の中に婚約者の姿を見つけぬか喜びすると、「それは彼女の来ていたドレスを剥ぎ取って着ているインディアンの女だ」と真実を告げる。動揺して詳しいことを聞こうとする婚約者に対して、ウェインは「俺が見たものを絵に描いて見せろとでもいうのか! 俺が生きている限り、二度とそのことを尋ねるんじゃない!」とだけ告げる。

『捜索者』© 1956 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.
観客は、殺された彼女の婚約者と同様にその死にざまを嫌でも想像させられるわけで、これは具体的なシーンが一切描かれていないにも関わらず、恐ろしいほど暴力的だ。
『スカーフェイス』や『グッドフェローズ』は何が新しかったのか?
さて、コードによる規制がなくなった結果、レイティングでR指定、PG-18指定とかになることを厭わなければ、どのような血なまぐさいバイオレンス・シーンでも描けるようになった。とはいえ、過激なシーンだけが売り物のスプラッター・フィルムなどは別として、作品そのもののクオリティがしっかりしたものである上にショッキングなバイオレンス・シーンが付加される映画というのは、何人かのトップ・ディレクターがいたからこそ世に出てきた。
ブライアン・デ・パルマ監督が、若手No.1スターの座に躍り出たアル・パチーノ主演で描いたギャング一代記『スカーフェイス』(1983年)は、古典的ギャング映画の名作『暗黒街の顔役』(1932年)のリメイクだが、のちに自身も映画監督として活躍するようになる若きオリバー・ストーンが手掛けた脚本は、舞台設定を当時のリアルタイムの1980年に変更し、マイアミに出てきたキューバ移民の主人公がのし上がる様をリアルに描いた。特に、初仕事の麻薬取引で取引相手に裏切られて相棒もろともチェーンソーで拷問を受けるシーンの凄まじさは、世界中で話題になったものだ。
同じくバイオレンスを自作のフレーバーとして用い続けてきたのがマーティン・スコセッシ監督。『グッドフェローズ』(1990年)では冒頭、いきなり死体を埋めるシーンからスタートするのだが、物語の後半になって、その埋められている男が撲殺される様子がショッキングに描かれる。同作品の恐ろしさは、単に視覚的なバイオレンス・シーンだけでなく、ジョー・ペシのキャラクターそのものが、味方であっても気が許せない変質的な暴力狂で、いつキレて爆発するかわからないところにあった。

『グッドフェローズ』デジタル配信中
ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
©1990 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
『スカーフェイス』のアル・パチーノにしてもそうだが、一流の俳優が、一流の脚本と一流の演出の許で出くわすバイオレンス・シーンだからこそ、この上ないスパイスとして効いてくることは間違いない。

『グッドフェローズ』©2015 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
時代とともに大きく変わってきた『007』シリーズの“拷問”シーン
イギリスのイオン・プロダクションによる『007』シリーズ(1962年~)も、第三作『007/ゴールドフィンガー』(1964年)辺りからは市場としてのアメリカを意識しハリウッド的な作りになってきたが、敵に捕らわれたジェームズ・ボンドが拷問を受けるシーンの描き方などは、如実に時代と共に変わっていることが判る。
たとえば、第四作『007/サンダーボール作戦』(1965年)では、身体のオーバーホールのために来ていた診療所で背骨を引き延ばす機械に体を固定して施術されている時に、敵に調節つまみを最大に引き上げられ、悲鳴を上げて失神する。だが、ボンドは看護師に救出された時に脂汗を流しながらも「これで身長が6インチは伸びたな」と軽口を叩くのだ。
https://www.instagram.com/p/CGZhxmZJFd1/
五代目ボンド、ピアース・ブロスナンの最終作『007/ダイ・アナザー・デイ』(2002年)では、プレタイトル・シークエンスで北朝鮮に侵入、武器を破壊して任務達成したかに思えたボンドが最終的に捕らえられ、タイトル・シークエンスでは彼が拷問で痛めつけられる様子が映される。そして本編が始まると、14か月に及ぶ監禁と拷問で体がボロボロとなったボンドが敵の捕虜との交換で英国に引き渡されるという、それまでにないシリアスな展開で期待を持たせた(が、その後の展開は荒唐無稽路線に戻ってしまう)。
4年間のインターバルを経て、ダニエル・クレイグの初お目見えとなった『007/カジノ・ロワイヤル』(2006年)では、原点回帰で第一作『007/ドクター・ノオ』(1962年)の頃のシリアスなボンドが戻ってきた。そのシリアスなボンドの象徴といえるシーンというのが、敵に捕らえられて裸で椅子に縛り付けられたボンドが鞭で睾丸を潰されそうになるという、見ているだけで痛々しい場面だった。
元々、イアン・フレミングの原作では拷問で指の骨を折られたりするシーン(「死ぬのは奴らだ」)もあったジェームズ・ボンド物だが、映画シリーズにおける拷問シーンの変遷を見ただけでも、その時代時代の描き方のトレンドが見て取れるのだ。
https://www.instagram.com/p/CPa1EkiInP2/
どちらがお好き? 想像力を刺激するプロダクション・コード時代/視覚的インパクトを追求する現代の表象
プロダクション・コードによって残酷シーンやエロティック・シーンに厳しい制限が加えられていた時代の映画と、CGやVFXの力を借りれば何でも描ける今日の映画とを比べて、どちらに軍配が上がるかは見る人それぞれの感性によって異なる。
『理由なき反抗』(1955年)でジェームズ・ディーンにプラトニックな愛を寄せるゲイのプレイトー(=プラトン)の描写は、現代の映画のように男同士でキスをするような直接的なものではなく、ディーンからもらった赤いジャンパーを愛おしそうに指で撫でるだけの奥ゆかしいものだ。それがコードの適用範囲内でのギリギリの表現だったことは間違いないが、そうした間接的な表現でゲイであることをほのめかすようなテクニックそのものが、コードの存在のおかげで発達してきたという側面もある。

ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD特別版 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
© 1955 Warner Bros Entertainment Inc. All Rights Reserved.
今の映画を見慣れた世代には、銃で撃たれても血も流れずにただ倒れるだけという昔の西部劇を嘘っぽいと感じるのは仕方のないことだが、同時に『Mr.ノーバディ』のような最新映画のバイオレンス・シーンもまた、それが“映画のウソ”であることを無意識のうちに感じ取っているからこそ、見ていてスカッとするのだろうし、痛々しすぎて眼を背けたくなったりはしないということではないだろうか? となると、これは進歩ではなく単なる好みの問題ではなかろうか?
文:谷川建司
『Mr.ノーバディ』は2021年6月11日(金)より全国公開
『Mr.ノーバディ』
主人公のハッチは、郊外にある自宅と職場の金型工場を路線バスで往復するルーティンで退屈な毎日を送っている。外見は地味で、目立った特徴もない。この世の理不尽なことを全身で受け止め、決して歯向かうことはない。世間から見れば、どこにでも居る何者でもない(NOBODY)、ただの男だ。自宅に2人組の強盗が侵入したときも、これ以上事態を悪化させないために、抵抗せず、黙って見過ごした。そんな威厳のない振る舞いに妻には距離を置かれ、息子からもリスペクトされることはない。ある日、ハッチが乗ったバスにジャックを試みるチンピラが乗り込んで来る。若い女性を獲物にし、「ジジイ」呼ばわりされたことで、ハッチは遂にブチ切れ大乱闘となる。この一件はその後、ロシアンマフィアへとつながり、銃撃戦、カーチェイスと派手にエスカレートしていくのだった……。
| 制作年: | 2021 |
|---|---|
| 監督: | |
| 出演: |
2021年6月11日(金)より全国公開