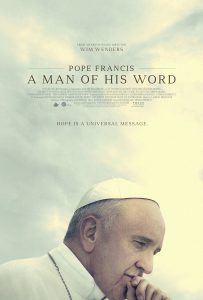「フランチェスコ」と呼んでほしかった「教皇フランシスコ」
【ポスターは映画のパスポート 第7回】
2019年に来日して長崎・広島を訪れた第266代ローマ教皇フランシスコは、Netflix配信と同時に劇場公開もされた『2人のローマ教皇』(2019年)がとても面白かったこともあって、キリスト教に無頓着なわれわれ日本人にも馴染みが深く、親しみが持てる存在だ。なんでも「フランシスコ」を名乗る教皇は歴史上初ということだが、どうして今までいなかったのだろうか。
それはともかくとして、「フランシスコ」は英語名で、アルゼンチン出身の枢機卿ホルヘ・マリオ・ベルゴリオは、教皇に選ばれたとき、イタリア語で「フランチェスコ」と名乗ったという。彼の母国語スペイン語ではフランシスコなのにもかかわらず。
ところが、カトリック中央協議会は「日本では“アッシジの聖フランシスコ”という呼び名が定着している」ので、「教皇 フランシスコ」で統一するようメディアなどに要請したんだそうだ。しかし、カトリック関係者はともかく、映画ファンにとっては最初から「フランチェスコ」としてくれたほうが良かったのに……と言っておきたい。
『ブラザー・サン シスター・ムーン』 裸足のフランチェスコはヒッピーに通ずる?
宗教としてのキリスト教にも、キリスト教の歴史にも興味のない日本人であろうとも、1970年代に外国映画に親しんでいた映画ファンだけは、ほぼ100%が『ブラザー・サン シスター・ムーン』(1972年)に大感動した記憶があるはずだ。普段はカンフー映画やカー・アクション、怪獣映画やアイドル映画ばかり観ていた中学生も、テレビ「水曜ロードショー」で『ブラザー・サン シスター・ムーン』を観た翌日は、みな心清らかにして親切で優しくなっていた(個人的には、サントラが発売されなかった主題歌をカセットテープに録音できて大よろこび)。

『ブラザー・サン シスター・ムーン』BROTHER SUN SISTER MOON
アメリカ ワンシート / 1972年 / パラマウント
USA 1-sheet / 102cm X 69cm / 1972 / Paramount
今回、もし、カトリック関係者の方が最初から「教皇はアッシジの“フランチェスコ”から名前を取りました」と大々的に発表してくれていれば、主題歌「ブラザー・サン シスター・ムーン」を唄いながら小鳥を追って素っ裸で屋根の上へ出て行く中・老年が世界中に出現したかもしれない。
劇映画の素材となった“フランチェスコ”をポスターと共に見ていこう。
宮殿に汚れた足で乗り込む中世の若者は70年代のヒッピーと同化していた
『ロミオとジュリエット』(1968年)で、従来の映画・演劇よりも実際の主人公の年齢に近い若者をキャスティング、16歳のオリヴィア・ハッセーがジュリエットを演じて自然なヌードシーンまで観せたこともあって、古典劇としては異例の世界的大ヒットを飛ばしたフランコ・ゼフィレッリ監督が、続いて“アッシジのフランチェスコ”の半生を映画化したのが『ブラザー・サン シスター・ムーン』だった。フランチェスコを演じたのはロンドン生まれ、当時24歳のグレアム・フォークナー。フランチェスコに心酔して出家する良家の子女クララ役には17歳のジュディ・バウカーが選ばれた。
アメリカ版ポスターは、フランチェスコが滝の前で出家するクララの髪を切る場面を宗教画のような画面処理と銀色のバックで上品にまとめている。
日本では、アメリカ版に準じたもの、クララを全面に押し出したもの、野原で花に囲まれるふたりをフィーチャーしたタイプの3種類が作られたが、いずれも宗教映画ではなく「愛の物語」として宣伝された。「文部省選定」の文字が大きいのも特徴だろう。中学や高校の学校団体上映(?)で見た人も多いかもしれない。

『ブラザー・サン シスター・ムーン』BROTHER SUN SISTER MOON
日本版半裁 スタイルB / 72.8cm X 51.5cm / 1973 / CIC
Japan Style B / B2 / 1973 / Cinema International Corporation
13世紀の話なのに、“フランチェスコ”の言動は1970年代のヒッピーたちに通じると気づかせてくれた本作。戦争に参加させられながらも、平和を望み、弱者を助け、贅沢や所有を拒否し、同じ考えの若者たちと一緒に町を出て野山で素朴に暮らす。神の声を聞き「神の家=教会」を建てようとするあたりは少し理解しにくいが、とにかく自分たちがやっていることが正しいかどうか、「神様の次に偉い人」のはずのローマ教皇に訊いてみようと裸足で旅に出る。フランチェスコの話を聞き、キリスト教の精神的な腐敗に気づいたローマ教皇(アレック・ギネス)は、ひざまづいてフランチェスコの汚れた足に接吻をする……。フランチェスコは、豪華なヴァチカン宮殿を去り、故郷の自然の中で素朴に暮らすことにする。大きく手を広げて野原をあゆむと、ドノヴァンの歌声が流れてくる。
すべてを捨てさり、全裸になって自然に向かうフランチェスコの姿を全面に打ち出したイギリス版のポスターは、マットな紙質も「質素さ」を感じさせ、美しい。

『ブラザー・サン シスター・ムーン』BROTHER SUN SISTER MOON
イギリス版ワンシート / 101cm X 68cm / CIC 1973 / CIC
UK 1-sheet / 1973 / Cinema International Corporation
ドノヴァンの歌う主題歌はなぜレコード化されていないのか
ところが、ザ・ビートルズと一緒にインドへ行ったり、マリファナで逮捕されたりしたことでも知られるシンガー・ソング&ライター、ドノヴァンの歌う素晴らしい主題歌は今まで一度もレコード化されていない。事情はいまだに分からないが、日本で公開された英語版では「音楽:ドノヴァン」と大きくクレジットされている。
ところが、のちにわかったことだが、本国イタリアで上映されたバージョンは「音楽:リズ・オルトラーニ」となっていて、ドノヴァンの名前は一切ない。オルトラーニは、あの『世界残酷物語』(1962年)の美しすぎる主題曲「モア」や『怒りの荒野』(1967年)のカッコよすぎるテーマを作曲した名作曲家だ。こちらはサントラ盤が出ていて(日本では未発売)、聴いてみると、まさしく同じ曲なのである。しかも歌っているのはカティーナ・ラニエーリなる女性歌手。このあたりに何か秘密があるのかもしれない。
ドノヴァンは、リズ・オルトラーニが作曲したイタリア語の歌を英語にして歌っただけだったのに、まるで映画全体の音楽すべてを担当したようにクレジットされてしまい、このままでは盗作と思われかねない……困ったあげくにサントラ発売を許可しなかったんじゃないだろうか、と類推している。中学生の時にテレビから録音し、その後はビデオテープやDVDから音を取り込んで自家製サントラを作った記憶のある人も少なくないのではないだろうか。
イタリア版オリジナルポスターには、もちろんドノヴァンの名はなく、フランチェスコの汚れた足と絢爛豪華なヴァチカン宮殿を対比させた印象的なデザインだ。

『ブラザー・サン シスター・ムーン』FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
イタリア版2フォーリ / 1972年 / ユーロ・インターナショナル・フィルム
Italy 2 fogli / 200cm X 100 cm / 1972 / EURO INTERNATIONAL FILMS
Netflix『2人のローマ教皇』では“あの人”が南米初の教皇を演じた
さて、話題のNetflixオリジナル作品『2人のローマ教皇』は、『羊たちの沈黙』(1991年)のアンソニー・ホプキンスが先代ベネディクト16世を、『未来世紀ブラジル』(1985年)のジョナサン・プライスが第266代ローマ教皇フランシスコを演じて、笑ってほろりとできるいい話になっていた。
意外なことに、監督は『シティ・オブ・ゴッド』(2002年)で衝撃を与えたブラジル出身のフェルナンド・メイレレス。フランシスコがアルゼンチンを回想する場面では、アルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』(2018年)を思わせる緊迫感を、ベネディクト16世とフランシスコが語り合う場面は、まるで猛獣使いのようにふたりの名優を手なずけて見せた。
教皇ふたりとも音楽好きで、ベネディクト16世はアビーロード・スタジオで録音したほどのピアノの名手でビートルズの曲を弾き、フランシスコは小用中に(ドノヴァンではないが)ABBAを歌ったりする。教皇に用意された伝統的な立派な靴ではなく、以前から自分の足になじんだボロボロの革靴を履き続けるフランシスコ教皇が“アッシジのフランチェスコ”の魂を継いでいるだろうことは確かに伝わってきた。
背景の建物が2つ並んだ十字架のようにも見える見事なシンメトリーの写真を使ったポスターは世界共通。コピーも文字の色なども統一されている(なぜか脚本家の名前が大きくなっているが、アメリカ版と同じなのだ)。日本版はB版の用紙サイズに合わせるために、上部が少しカットされているようだ。

『2人のローマ教皇』The Two Popes
日本版 B1 / 2019 / Netflix
Japan B1 / 103cm X 72.8cm / 2019 / Netflix
Netflix映画『2人のローマ教皇』独占配信中
アメリカ版ポスターを見ただけで邦題が決まった(?)ハリウッド製シネマスコープ大作
第二次大戦後しばらくして、1950年にイタリア・ネオレアリズモの巨匠ロベルト・ロッセリーニ監督が『神の道化師、フランチェスコ』を撮っている。もちろん、白黒スタンダード画面で、やせ細ったフランチェスコと仲間たちが、バカ騒ぎしたり歌を唄って空腹をまぎらわせてばかりいるようで、観ていてお腹がすいてくるほど真摯で禁欲的で真面目な伝記だ。教会へ通うような真面目な人か、映画史を学ぶ研究者ぐらいしか見る機会はなさそうだ。
1961年には、ハリウッドがカラー・シネマスコープ大作を作っている。20世紀フォックスの『剣と十字架』だ。監督は『カサブランカ』(1942年)のマイケル・カーティス、主演は当時31歳、カリフォルニア生れのアメリカ人ブラッドフォード・ディルマン。英語原題は「アッシジのフランシス」だ。華やかな鎧を着てシチリアへ出陣するくだりなど、さすがハリウッド映画と思わせる豪華な衣装やセットはきれいすぎるし、出家してからの僧侶たちもボロ着というより小ぎれいだ。サハラ砂漠を越えてアラブの王(ペドロ・アルメンダリス)に会いに行くエピソードもあるが、厳しすぎる戒律を嫌う仲間たちとの葛藤が物語のメインで、結局は裏切られ、フランシスは眼が見えなくなって死んでしまう……。
シネマスコープのアメリカ映画を好むタイプの観客にはアピールしたかもしれないが、日本の配給会社は「アッシジのフランシス」も「フランチェスコ」も日本人は誰も知らないと判断したのか、邦題はアメリカから届いたオリジナル版のポスターを見ただけで決めたようだ。

『剣と十字架』FRANCIS OF ASSISI
アメリカ 3シート / 1961年 / 20世紀フォックス
USA 3sheet / 206cm X 104cm / 1961 /20th Century Fox
ミッキー・ロークがフランチェスコ!? ミスキャストを越えて現代のネオ・レアリズモを目指した女性監督
1989年には、『愛の嵐』(1973年)で知られるイタリアの女性監督リリアナ・カヴァーニが、なんとミッキー・ロークを迎えて『フランチェスコ』を撮っている。
地味な題材なのに製作費が集まったのは、『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』(1985年)や『ナインハーフ』(1985年)で注目されていたロークのネームバリューのおかげだし、全身泥だらけになったり、全裸で雪原を駆けまわったり、体を張って演じているのは確かだが、いかんせんウェイトオーバーというか、筋骨隆々たる肉体美を誇る“ミッキー”フランチェスコは違和感がはなはだしい。カヴァーニの演出は、裸に剥かれた戦死者が大量に埋められる場面を観せたりする現代的なネオ・リアリズモ・タッチなので、ヘアスタイリストが整えたようなロークの80年代型最新ヘアスタイルも少々困りものだった。

『フランチェスコ』
日本版半裁 / 1990 / 大映
Japan B2 / 72.8cm X 51.5cm / 1990 / Daiei
とはいえ、ボクサー志望で日本へボクシング・マッチにやってきたこともあるローク(猫パンチ)や、ティム・バートンのパートナーとしてやんちゃな演技を見せることが多いヘレナ・ボナム・カーターが、“アッシジのフランチェスコ”のために、イタリアまで出かけて出演したことは記憶にとどめたい。音楽がヴァンゲリスのシンセサイザーなのも異彩を放っていた。
日本では、初公開時より22分長い『フランチェスコ ―ノーカット完全版―』が2008年に公開された。また、リリアナ・カヴァーニは1966年と2013年にもフランチェスコ物語をテレビ用に撮っている。よほどフランチェスコに心酔しているのだろう。

『フランチェスコ』FRANCESCO
イタリア ビデオポスター / デルタ・ビデオ / L&M ADV.ミラノ
Italy Video-poster / 49.5cm×35cm / DELTA VIDEO / L&M ADV.MILANO
21世紀の“アッシジのフランチェスコ”の姿をヴェンダースが記録した『ローマ法王フランシスコ』
第266代ローマ教皇フランチェスコ(イタリア語読み)は、もちろん“アッシジのフランチェスコ”に敬意を込めて同じ名前を名乗っているのだが、そのあたりの事情が一番分かるのが、ドイツのヴィム・ヴェンダースがローマ教会に依頼されて撮ったドキュメンタリー『ローマ法王フランシスコ』(2018年)だろう。日本ではラテンビート映画祭で上映されたのちにNetflixでも観られるようになっていた(現在は配信なし)。
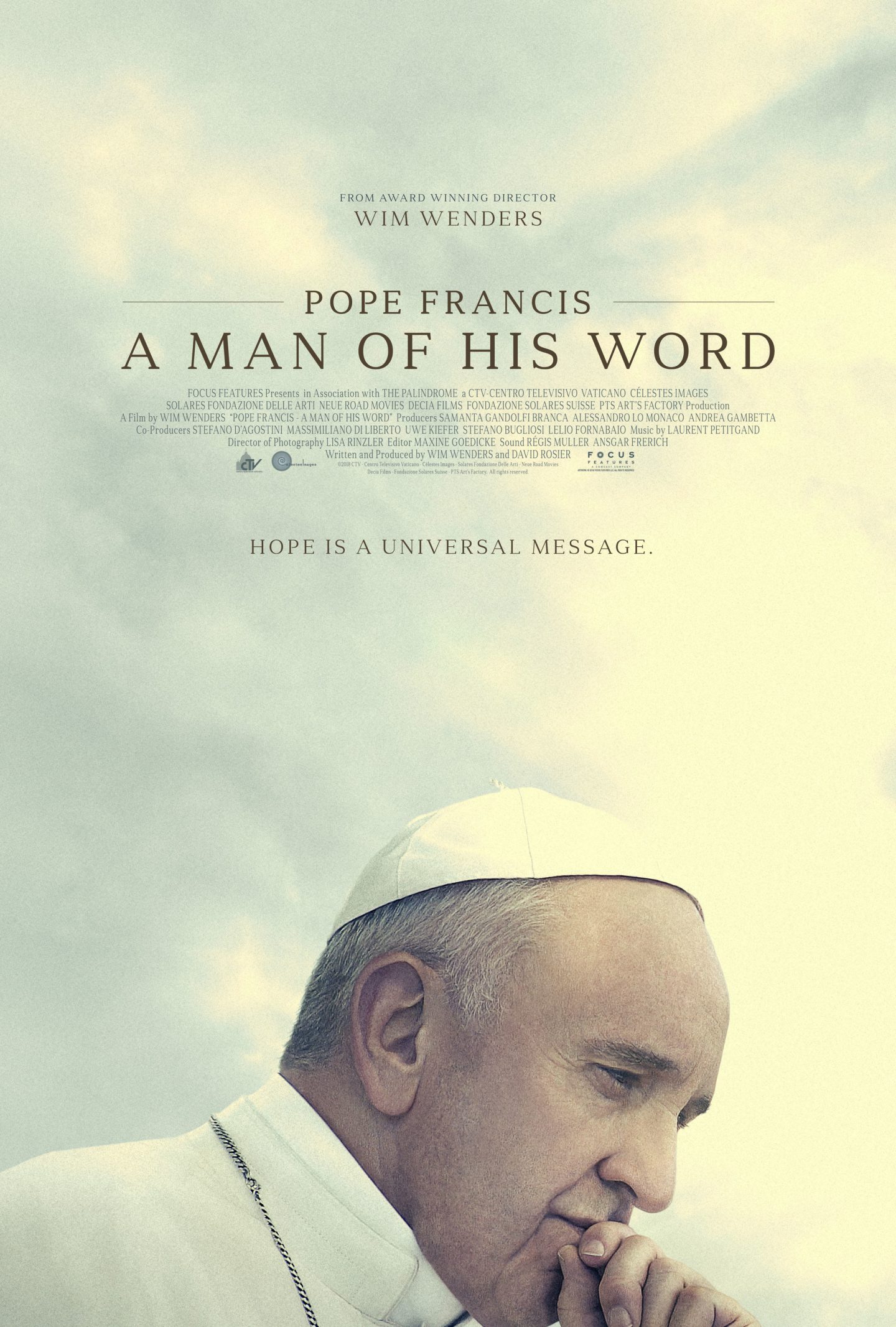
『ローマ法王フランシスコ 』POPE FRANCIS:A MAN OF HIS WORD
アメリカ版ワンシート / 2018年 / デザイン:P+A
USA 1-sheet / 104cm×69cm / 2018 / Design: P+A
ヴェンダースは教皇と1対1で向かい合って質問をぶつけていく。環境問題、核、同性愛や小児性愛問題にまで踏み込んだ会話がなかなかスリリングだが、同時に教皇が世界中をめぐって人々に接する記録を見ることができる。護衛の車より小さなファミリー用乗用車に乗り(ミスター・ビーンみたいだと笑われる)、カートのような車でパレードし、信者たちと手を取り合い、囚人の足を洗って接吻する様子は、“アッシジのフランチェスコ”が行ったことの現代版アレンジといっていい。神の声が「我が家を立て直すのだ。いまにも崩れてしまう」と言っているというのもうなずける。
13世紀も21世紀も、問題を抱えていることに違いはない。「自己批判や改善をしない組織は健康診断をしない人と同じ」「買いだめという病」「物を持ちすぎることなくつつましく生きるべき」「生き方を変える必要がある」という教皇の言葉は、そのまま新型コロナ時代のいまにも通じる。
ヴェンダースは、わざわざ“アッシジのフランチェスコ”の挿話を再現ドラマとして挿入する。無名の俳優が演じる“アッシジのフランチェスコ”が、十字軍に反対してわざわざイタリアから中東まで出かけて行ったことをドラマ風に見せる。そして、現代の“教皇フランチェスコ”はエルサレムに出かけて、“壁”に語りかける。ドキュメンタリーのエンディングには、パンク・ロック詩人パティ・スミスの力強い歌が流れてなかなか感動的だ。
『ローマ法王になる日まで』~社会派サスペンスのような緊迫感
教皇フランシスコの半生を描いた伝記映画『ローマ法王になる日まで』(2015年)もある。少し前にヴァチカンから逃げ出してしまう教皇を描いたコメディ『ローマ法王の休日』(2011年)を撮ったイタリアの才人ナンニ・モレッティの助監督をしていたダニエーレ・ルケッティが撮ったイタリア映画だ。
一般公開題名はまるで教皇の立身出世物語のようだが、全然違う。教皇となる以前、ホルヘ・マリオ・ベルゴリオ司祭が軍事政権下アルゼンチンで体験した事実を再現したドラマで、まるでコスタ=ガヴラスの社会派サスペンスを観ているような緊迫感がある。傍若無人な軍部の非道になすすべもない聖職者の無念が伝わる。公開前のイタリア映画祭では原題通り『フランチェスコと呼んで -みんなの法王』として上映されたらしいが、司祭になる試験で「日本へ布教に行きたい」と抱負を述べていたことにちょっとびっくり。

『ローマ法王になる日まで』CHIAMATEMI FRANCESCO – IL PAPA DELLA GENTE
日本版 B1 / 2017年 / シンカ/ミモザフィルムズ
Japan B1 / 103cm X 72.8cm / 2017 / Synca/Mimosa Films
文:セルジオ石熊
『ブラザー・サン シスター・ムーン』はAmazon Prime Videoほか配信中