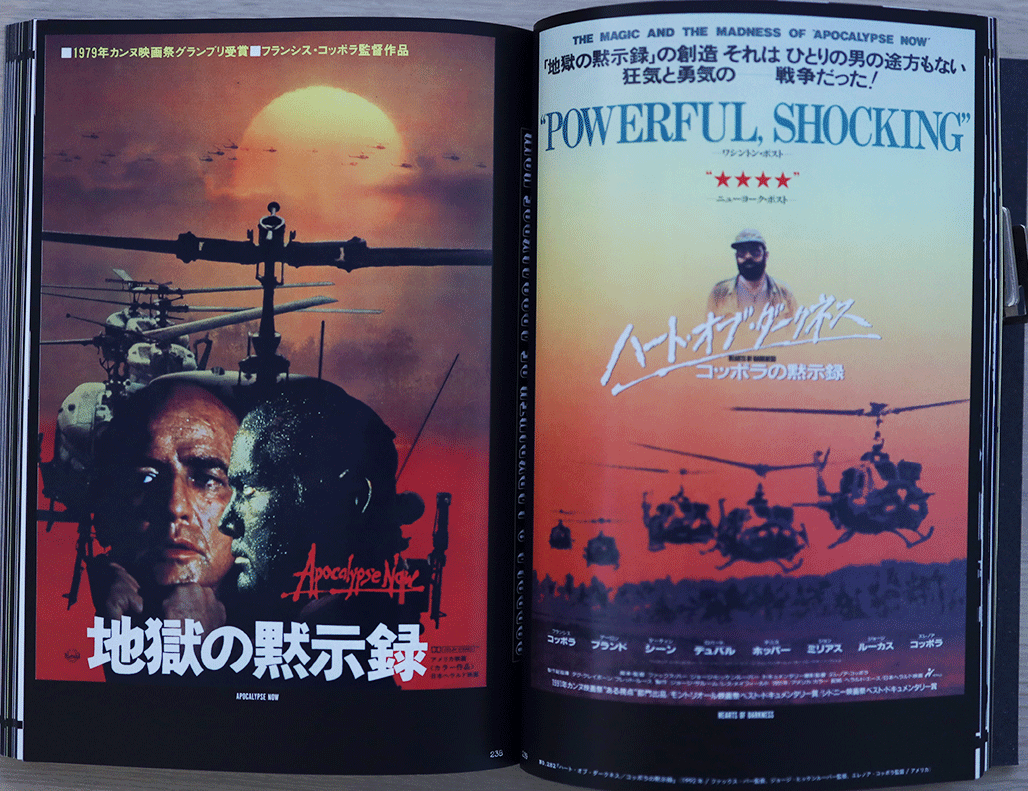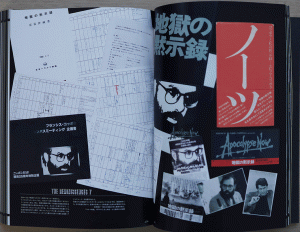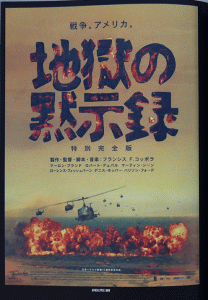【映画宣伝/プロデューサー原正人の伝説 第6回】
日本ヘラルド映画の伝説の宣伝部長として数多の作品を世に送り出すと共に、「宣伝」のみならず、映画プロデューサーとして日本を代表する巨匠たちの作品を世の中に送り出してきた映画界のレジェンド原正人(はらまさと)。全12回の本連載では、その原への取材をベースに、洋画配給・邦画製作の最前線で60年活躍し続けた原の仕事の数々を、原自身の言葉を紹介しつつ、様々な作品のエピソードと共に紹介していく。原への取材および原稿としてまとめるのは、日本ヘラルド映画における原の後輩にあたる谷川建司。
ヘラルドの黄金期と言われる時期はいくつかあるが、とりわけ連載第1回で紹介した『エマニエル夫人』(1974年)に始まる一連の大ヒット作品の数々は洋画配給会社が世の中に大きな流行を作り出していくことができた、そんな時代のバイタリティを感じさせる。

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)
第6回目の本稿は、外国映画の配給会社であった日本ヘラルド映画が、映画そのものを製作していく領域に進出していった背景として、映画の製作開始前の段階からコミットした作品としては最大の賭けであり、かつ底なし沼に入り込んでしまったかの如くトラブル続きで混迷を極めた、フランシス・フォード・コッポラ畢生の大作『地獄の黙示録』(1979年)にまつわる話を紹介しよう。
撮影トラブル連発! コッポラの『地獄の黙示録』を資金面で支えたヘラルド古川社長
1972年の『ゴッドファーザー』、1974年の『ゴッドファーザーPART II』でオスカーを連続して総なめにしたフランシス・フォード・コッポラ監督が、超大作となる次回作の製作資金を捻出するために、日本と東南アジアでの配給権譲渡の見返りとして300万ドル(当時のレートで約9億円)の出資をヘラルドに打診してきたのは、1975年10月のことだった。米国配給はユナイトに決まっていたものの、コッポラ自身にとってもかつて取り組んだことのないほどの大規模な作品だったため、製作資金を確保するためには日本と東南アジアにプリ・セールス(先に配給権を売って、そのお金を映画製作費につぎ込む形)をかけるしかなかったのだ。
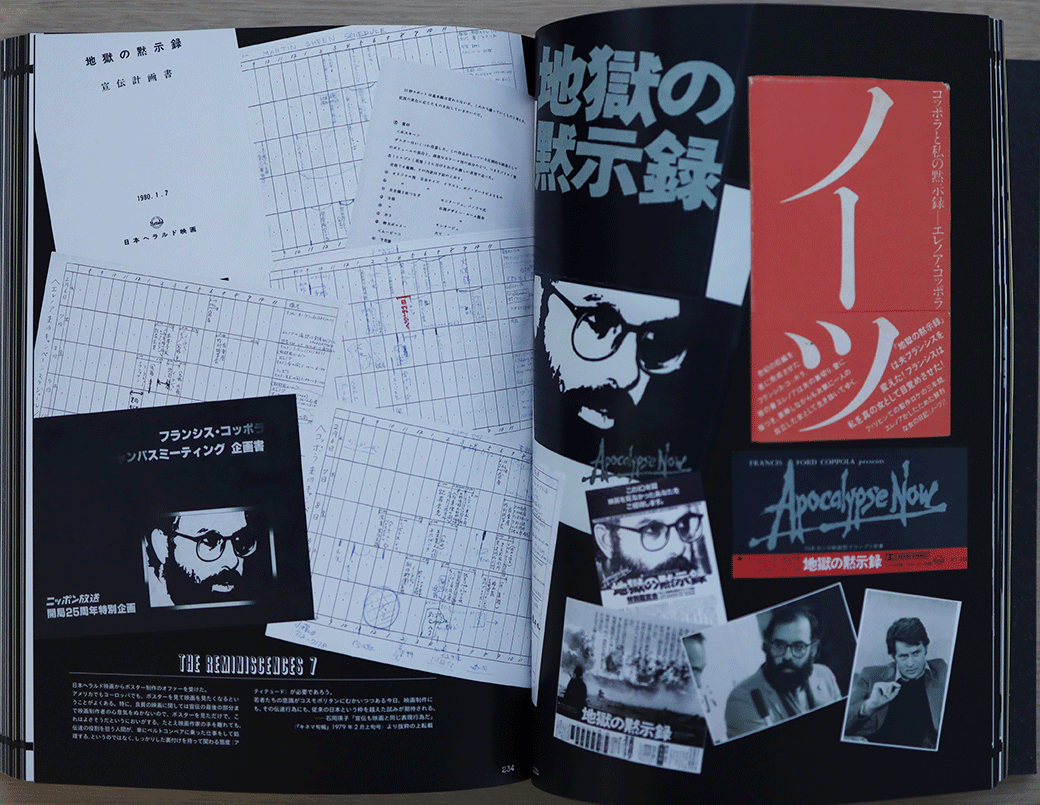
日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)
実はコッポラは、ヘラルドよりも先に松竹傘下の富士映画(後の松竹富士)に話を持ち掛けていたものの、富士映画は別の超大作『遠すぎた橋』(1977年)の配給権を取っていたために、コッポラの話を断っていたのだという。『エマニエル夫人』(1974年)の大ヒットで上げ潮ムードだったヘラルドは、このコッポラの賭けに乗った。もちろん、ヘラルドとしても失敗すれば会社の屋台骨がぐらつくことになる大博打である。
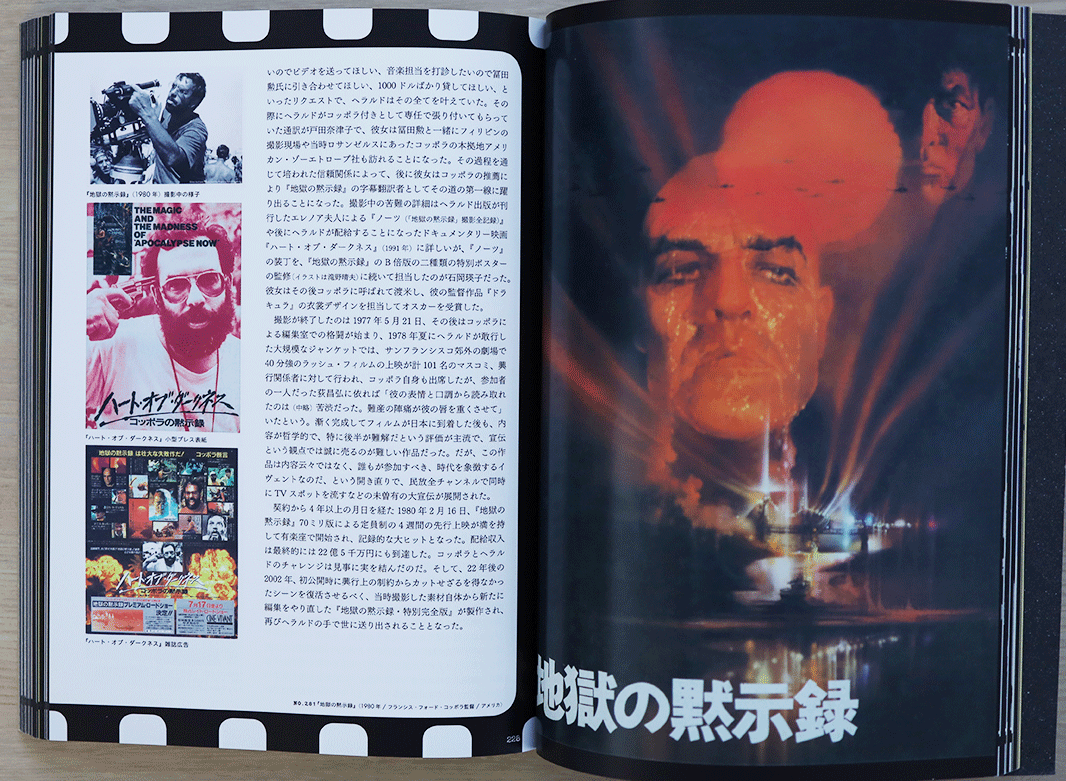
日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)
『地獄の黙示録』は、かつてオーソン・ウェルズが映画化への執念を見せたものの断念したというジョゼフ・コンラッドの「闇の奥」を原作とし、舞台を現代のベトナム戦争に置き換えた意欲作だ。出演者としては、スティーヴ・マックイーン、ジーン・ハックマン、ロバート・レッドフォード、リノ・ヴァンチュラ、そしてマーロン・ブランドといった名だたるスターが予定されていた。だが、撮影開始は延期を重ね、ハックマンが予定されていたキルゴア大佐にはロバート・デュヴァル、レッドフォードと交渉していたカメラマン役にはデニス・ホッパー、ヴァンチュラが断ってきたフランス人入植者にはクリスチャン・マルカンが確定し、いよいよ1976年3月にクランクインという時になって、主役のマックイーンが土壇場で降板することになった。
コッポラはヘラルドに国際電話を掛け、「契約の根幹にかかわる重大な変更事項なので、今なら製作参加を白紙にできるが、どうするかを決めてほしい」と決断を迫ったのだが、古川勝巳社長は「買ったのはマックイーンの映画じゃない。コッポラの映画だ」とコッポラへの支援を即決したという。ヘラルドが撤退していれば世界中のその他のプリ・セールス先も動揺して資金を引き揚げ、映画の製作自体が中止に追い込まれる可能性が強かったため、ヘラルドの支援はまさしくコッポラの窮地を救うことになった。
だが、『地獄の黙示録』は1976年3月20日にフィリピンで撮影を開始したものの、今度はマックイーンに代わって主役を演じることに決まったハーヴェイ・カイテルが僅か1週間で解雇され、マーティン・シーンへ変更。記録的な規模の台風が直撃してセットが破壊され作り直しとなる、撮影中にマーティン・シーンが心臓発作を起こして一時撮影中断となる、などトラブル続きで、1977年5月21日に撮影が完了した後も、今度は編集室での格闘が続き、漸く完成してフィルムが日本に到着すると、内容が哲学的で、特に後半が難解だという評価が多く、実に宣伝するのが難しい作品となっていた。
「誰もが参加すべき歴史的イベント!」という売り文句を掲げ連日ソールドアウト
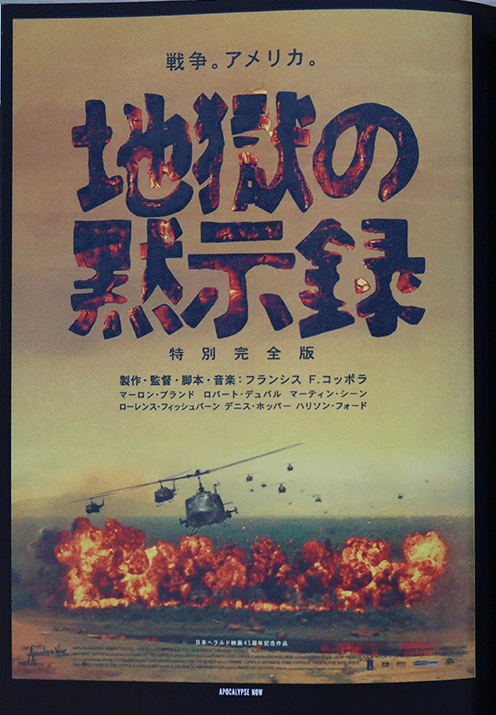
日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン(パイ インターナショナル刊)
やっとの思いで最終編集を終えたコッポラは、エンドロールは未編集のまま、第32回カンヌ映画祭(1979年)に出品。映画祭では、コッポラ・ファミリーは海から大型ヨットでカンヌへ乗り付け、関係者を郊外のレストラン<ロアシス(L’Oasis)>に招いて食事会が開かれた。
「家族やスタッフ、各国の配給会社を代表する人々のいる食事会の席では、コッポラは自ら隣の席に古川社長を座らせ、“あの時、フルカワが応援してくれたおかげでこの作品を続けることができた”と感謝の言葉を述べ、杯を上げてくれました。あの光景は、今でもとても誇らしい記憶として心に残っています」
日本での劇場公開にあたって、原率いる宣伝チームは、「この作品は内容云々ではなく、誰もが参加すべき、時代を象徴するイべントなのだ」というある種の開き直りで、民放全チャンネルで同時にTVスポットを流すという未曽有の大宣伝を展開。さらに、作品の大作感・イベント感を演出するために、あえて東京の有楽座のみで70ミリフィルム版での先行ロードショーとし、しかも全席指定でチケットの前売り販売をするという作戦で(当時は自由席が一般的)、作品そのものの難解さというハンデを逆手に取って、一大キャンペーンを繰り広げたのだ。

原曰く、
「日程表を新聞広告に入れ、毎日「この日は満席です」と満席の日を塗りつぶしていくのです」
結果、「このイベントに乗り遅れてはダメだ」というムードを作り上げ、最終的には1980年2月16日からの1ヶ月間、有楽座は全席売り切れとなり、その後の全国展開でも記録的な大ヒットとなった。
まさに“地獄”のような大作への賭けに勝利! 新会社ヘラルド・エース設立へ
『地獄の黙示録』以前にも、イタリアで日本人観客向けのお涙頂戴もののラブ・ストーリー『ラストコンサート』(1976年)に製作費を投入するというような経験は積んできたヘラルドだったが、『地獄の黙示録』は何といっても当時の映画史上最大の製作費を費やした空前絶後の大作であり、原は
「『地獄の黙示録』という難しい作品をヒットさせたことは、僕にとっての勲章ともなりました」
と語っている。
この『地獄の黙示録』という賭けに見事に勝った原は、その大成功を置き土産に、今度はヘラルドから暖簾分けの形で、新会社ヘラルド・エースで自らが社長を務めることとなった。このヘラルド・エースのコンセプトは、良質なアート系作品を小さなマーケットでビジネスにしていくことと、日本映画の製作へコミットをしていくこと、という二つの明確な方針によって示されていた。そして、『地獄の黙示録』の製作現場の修羅場を見聞きすることで、今度は原自身が映画プロデューサーとして様々な作品を実際に製作していく上での土台のようなものが培われたのだろう。
だが、『地獄の黙示録』公開から4年後の1984年、原はプロデューサーとしての地獄を経験することになる。それこそが、ヘラルド・エース最大の挑戦にして、原のプロデューサー人生における最大の挑戦でもあった、黒澤明監督作品『乱』(1985年)製作の経緯なのだが、それはまた次回に詳しく述べることにしよう。
文:谷川建司
第6回:終

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン
『エマニエル夫人』『地獄の黙示録』『小さな恋のメロディ』など、日本ヘラルド映画が送り出した錚々たる作品の宣伝手法、当時のポスタービジュアルなどを余すところなく紹介する完全保存版の1冊。
著・谷川建司 監修・原正人/パイ インターナショナル刊