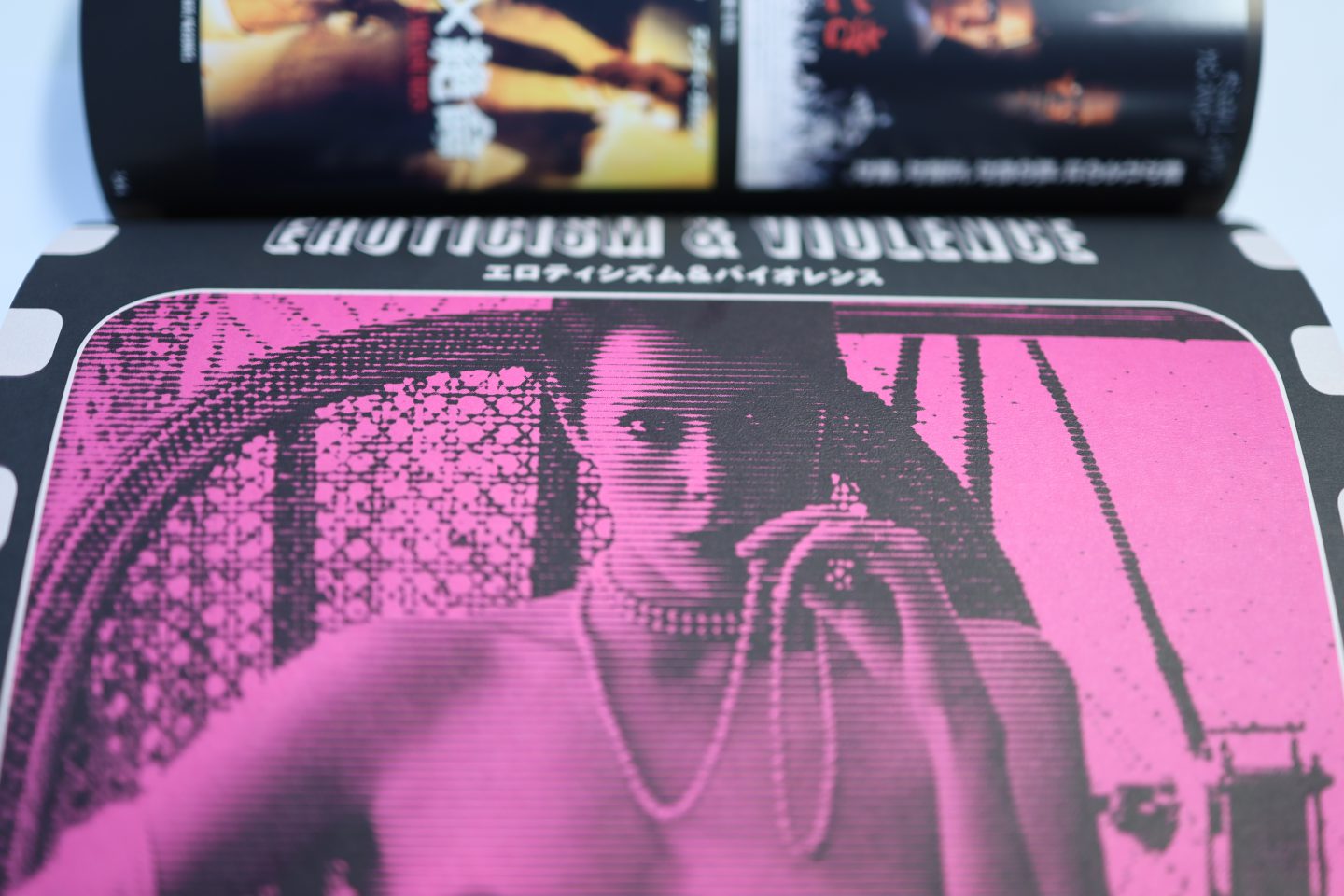日本映画界を席巻したレジェンド宣伝部長、原正人とはどんな男だったのか?
前身の欧米映画社を含め1956年から半世紀の間存在した(後に角川映画が吸収合併)洋画配給会社、日本ヘラルド映画(代表的な配給作品:『小さな恋のメロディ』『気狂いピエロ』『地獄の黙示録』『ゾンビ』『エルム街の悪夢』『ニュー・シネマ・パラダイス』『レオン』ほか多数)。同社の宣伝部長として数多の作品を世に送り出し、後にヘラルドエース、エース・ピクチャーズ、アスミック・エースといった映画配給会社を設立した男が原正人(はらまさと)だ。“宣伝”だけでなく、映画プロデューサーとして日本を代表する巨匠たちの作品を世のなかに送り出してきた、映画界のレジェンドである。
全12回を予定しているこの連載では、本人への取材をベースにその言葉を紹介しつつ、洋画配給・邦画製作の最前線で60年活躍し続けた原の仕事の数々を、ヘラルド時代の後輩でもあった映画ジャーナリスト・谷川建司が様々な作品のエピソードと共に紹介していく。第1回目は、ヘラルド最大の大ヒット作である『エマニエル夫人』に関する伝説を紹介したい。

「日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン」より(パイ インターナショナル刊)
“宣伝はクリエイティヴなもの”という考えから「宣伝プロデューサー」という肩書を考案した男
映画の仕事の中でも花形のポジションとして「宣伝プロデューサー」という肩書がある。邦画・洋画を問わず今日ではどこの会社でも使われている肩書だが、この言葉を発明した人物こそ、実は原正人である。
1960年代当時、原は日本ヘラルド映画の宣伝部長。その当時は、アメリカに本社のある“メジャー”と呼ばれる映画会社と、自ら欧米等の映画を買い付けて配給する“インディペンデント系”と呼ばれる日本独自の配給会社とがあり、その“インディペンデント系”の中でも東宝東和のような戦前からの伝統ある洋画配給会社などがある中、戦後設立のヘラルドは新興洋画配給会社という立場だった。そして、老舗に追い付け追い越せとばかりに、他社が思いもつかないような大胆な宣伝の仕掛けでB級の作品を大ヒット作に化けさせ、映画業界のみならずマス・メディア界全般にその名を轟かせた “伝説の人”こそが 、まさしく原正人だったのだ。
当時の原は、斬新な広告を次々に打ち出していたアメリカの広告代理店・DDBがモットーとしていた“宣伝はクリエイティヴでなくてはならない”という言葉をヒントに、宣伝部員の精鋭たちが個々の担当する作品をどうやって世に知らしめ売り込むのか、その自由な発想やアイデアを存分に出せるシステムや風土を作るために「宣伝プロデューサー」という肩書を考案したのだという。もっとも、若手宣伝部員たちは日々映画の売り込みに奔走、酒の飲めない原に代わって夜の付き合いにも精を出し、結果、翌日の定時出社には遅刻してくるというのが常態化していたというが、彼らに残業手当を付けることはできないため、彼らにとっては「宣伝プロデューサー手当」は大いにモチベーションを高めることにもなったようである。もちろん、原の下で育っていった「宣伝プロデューサー」は今日でもなお数多く映画業界に存在する。
エロ映画に女性向け作品としての可能性を見出したマジック!?

「日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン」より(パイ インターナショナル刊)
ヘラルドの半世紀の歴史の中で最も“儲かった”映画といえば、ダントツで『エマニエル夫人』だ。何しろ、ヘラルドはこの作品の音楽著作権なども含めたオール・ライツ買い切り(売り上げに応じた追加の支払いが無い形)の2千万円程度で購入し、収入のほうは劇場の配給収入だけで15.6億円(当時)もの記録を打ち立てている。ちなみに、当時の物価では大卒初任給が8万円ほど(現在は20万円)、はがき一枚10円(現在は62円)だったから、15.6億円というのは今ではその3倍から6倍もの金額ということになる。それに、現在では映画の売り上げというのは興行収入(映画館の売上合計)を基準としているが、当時は興行収入から映画館の売り上げを差し引いた配給会社の収入である配給収入を指針としていたから、なおさらスゴイ数字ということになるのだ! 配給収入だけならこれを上回る作品は他にもあるが、安く買って沢山儲けるが一番おいしいわけだ。
では、どうして『エマニエル夫人』が2千万円で買えたのかというと、買った時点では誰もが三流ポルノ映画としか思っていなかったから。実際、『エマニエル夫人』は、初め成人映画としてポルノティックな路線で公開することを想定しており、劇場も当時存在していた成人映画も上映可能である丸の内東宝系にオファーするつもりだったというが、フランスのファッション写真家フランシス・ジャコベッティの特写による籐の椅子に裸で座るシルビア・クリステルの写真(『エマニエル夫人』とは何の関係もない写真)を担当の宣伝プロデューサー・山下健一郎が写真エージェンシーのオリオンプレスで見つけてきて、これに100万円(当時)も払ってポスターのキー・ビジュアルとして使ったことで、急に宣伝部の中で「これはもしかしたら女性映画としても行けるんじゃないか」という声が上がってきたという。もちろん、一般映画として映倫の審査もクリアしなければならないため、大幅な修正が必要となるのだが、原は全社一致団結して女性客中心に売り込む作戦をたて、その意向に沿った形で営業部が女性映画上映のイメージがある日比谷のみゆき座でのロードショー公開を実現させることに成功したのだ。
原自身は、部下にのびのびと仕事をさせ、ポスターのビジュアルにしろ、キャッチ・コピーにしろ、下から上がってきたアイデアに対して、最終的にそれを決定する立場にあったわけだが、
「僕自身はけっして新しい制度や方針を次々に取り入れて、業界や世の中をあっと言わせるようなイノベーターではなく、むしろ「オーガナイザー」、周りの才能やアイデア、パワーを結び付けて、彼らが最大限に力を発揮できる場を作ってきただけ」
と、成功したのはすべて周りの人たちのお蔭とばかりに謙遜する。
「みゆき座での公開にあたっては、営業部が東宝の当時営業本部長だった松岡功さん(現・東宝名誉会長)にお願いをして、正月興行にまでしてもらうことができたことが大きかったんだよ」
あやかりたい! 儲かりすぎて社員にボーナス20ヶ月
ところで、ヘラルドでは、作品が儲かったときには社員に還元するという古川勝巳社長の考えがあった。
「だから新橋駅前ビル、ツーフロア買ったんですよ。あんまり儲かりすぎて、社員にボーナスを20ヶ月。伝説みたいに(笑)。……当時、会社が面倒みるから家を買っとけ、マンションを買っとけってといってね。ボーナスを頭金にして、住宅ローンの契約を会社が支援する形で、マイホームを持つ事を勧めたんですよ。あの時代のやつは僕も含めてみんな、あれで人生の基礎を作ったんです。やっぱりお金は大切だって、本当に思いましたね」
今の世の中ではちょっと考えられないうらやましい話だが、『エマニエル夫人』大ヒットというのもけっして降ってわいた話ではなく、ヘラルドには、古川社長が「お客さんの心を掴むにはエロが必要」との持論(?)を持っていたこともあり、エロチック映画に関しても冒険的な試みの蓄積が相当にあったのだ。

「日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン」より(パイ インターナショナル刊)
1960年代には『濡れた砂丘』『濡れた夜』の“濡れたシリーズ”や『花弁が濡れるとき』『花弁のうずき』の“花弁シリーズ”、来日させたヒロイン役のサンドラ・ジュリアンの“裸の記者会見”を敢行してマスコミ業界の話題を独占した1971年の『色情日記』から1980年代の『カリギュラ』『ナインハーフ』といった作品まで、文芸大作やファミリー向け映画を当てる一方で、ゲテモノのホラー映画やエロチック映画まで何でも扱っていた。
「後発の映画会社だったヘラルドは、当時100人近い社員を抱えていた。彼ら社員を食わせるためには、とにかく何でもやるしかなかったんだね。だからこそ、“悪食”であろうと、どんな映画にも取り組んだ」
ヨーロッパの薫り高き名作映画ばかりを買えれば苦労はしない。でも、実際には後発の会社だから買える作品というのも二流の作品が多い。そんなヘラルドだからこそ、二流の作品を一流の作品に化けさせ、予期せぬ大ヒットに結びつけてしまうバイタリティがあったのだろう。“ボーナス20ヶ月伝説”の裏には、原正人率いるヘラルド宣伝部のそんな事情があったのだ。
第1回:終

日本ヘラルド映画の仕事 伝説の宣伝術と宣材デザイン
『エマニエル夫人』『地獄の黙示録』『小さな恋のメロディ』など、日本ヘラルド映画が送り出した錚々たる作品の宣伝手法、当時のポスタービジュアルなどを余すところなく紹介する完全保存版の1冊。
著・谷川建司 監修・原正人/パイ インターナショナル刊