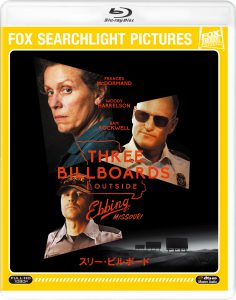『スリー・ビルボード』と『さよならの朝に約束の花をかざろう』母の原動力は本当に母性だったのだろうか?【アッチ(実写)もコッチ(アニメ)も】

『スリー・ビルボード』で描かれる強烈な“母親”像

『スリー・ビルボード』Ⓒ2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
娘がレイプされ、焼き殺されてしまった母親がいる。映画『スリー・ビルボード』(2017年)の主人公、ミルドレッド・ヘイズだ。ミルドレッドは警察の捜査が進まないことに業を煮やし、道路沿いの広告板に「娘はレイプされて焼き殺された」「未だに犯人が捕まらない」「どうして、ウィロビー署長?」というメッセージを貼り出した。

『スリー・ビルボード』Ⓒ2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.彼女の頑なすぎる態度は、地元警察の署長を信頼する地域の住民の反発を招き、彼女の息子もまた、彼女のやり方を非難する。ミルドレッドを突き動かしているものはなにか。それは母親としての愛なのか。

スリー・ビルボード
ブルーレイ発売中
¥1,905+税
20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン
(C)2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.
物語が進むと、ミルドレッドが娘について自責の念を抱えていることが明らかになる。事件当日、娘が車を貸してほしいと頼んだ時、普段の娘の素行の悪さに腹を立てていたミルドレッドは車を貸すのを断っていた。それだけでなく、口論の挙げ句に「暗い夜道を歩いてレイプされたらどうするの?」と食ってかかる娘に「レイプされればいい」と言い返していたのだ。
ミルドレッドは本当に犯人を捕まえたいのか。彼女の抱えた屈託を知ると、周囲に過剰に攻撃的なのは、自分の抱えきれない葛藤を吐き出すためのようにも見える。そこに浮かび上がるのは、普遍的な「母の愛」というよりも、利己的にすら見える“そうせざるを得ない”一人の人間の魂だ。
https://www.youtube.com/watch?v=0sjdr0IsARM
絶望の淵でなお、命をつなごうとする少女
そうせざるを得ない。だから、そうやって行動してしまう人は少なくはない。ミルドレッドのような過激さはないが『さよならの朝に約束の花をかざろう』(2018年)の主人公マキアも、そんな感情に突き動かされたキャラクターだ。

『さよならの朝に約束の花をかざろう』© PROJECT MAQUIA
マキアは、数百年は生きるという伝説の種族イオルフの少女。ある日イオルフの里は強国に襲われ、命からがら逃げ延びたマキアは、偶然、賊に襲われた一家を見つける。そこにはただひとり赤ん坊が生き延びていた。マキアはその赤ん坊を拾い、育てることを決意する。なにができるわけでもないひとりぼっちのマキアは、どうして赤ん坊を育てようと思ったのか。
「母性本能に突き動かされた」と見る人もいるだろう。あるいはひとりぼっちのマキアが、天涯孤独であることを知らずに、しかし生きようとする赤ん坊の姿に共感したととらえることもできるだろう。だがマキアのセリフをみると、そうした2つの要素に収まらないなにかも顔をのぞかせている。

『さよならの朝に約束の花をかざろう』© PROJECT MAQUIA
母の愛か、ひとりの人間としてのエゴか

『さよならの朝に約束の花をかざろう』© PROJECT MAQUIA
マキアが赤ん坊を拾おうとする、その場に居合わせた男は「おもちゃじゃないんだぞ」とマキアをたしなめようとする。それに対してマキアは「おもちゃじゃありません」と答え、「私のヒビオルです」と続ける。
“ヒビオル”とはイオルフだけが織ることができる特別な織物。イオルフは、ヒビオルの織り目の中に自分たちの日々の出来事を織り込み、長い時を生きてきた。赤ん坊を「私のヒビオル」と呼ぶということは、この赤ん坊をマキアにとって日々の暮らしの記録とし、生きた証にするということである。なにもかも失った孤独なマキアにとって、赤ん坊を育てようとすることは、自分を支えていくために“そうせざるを得ない”ことだったのだ。
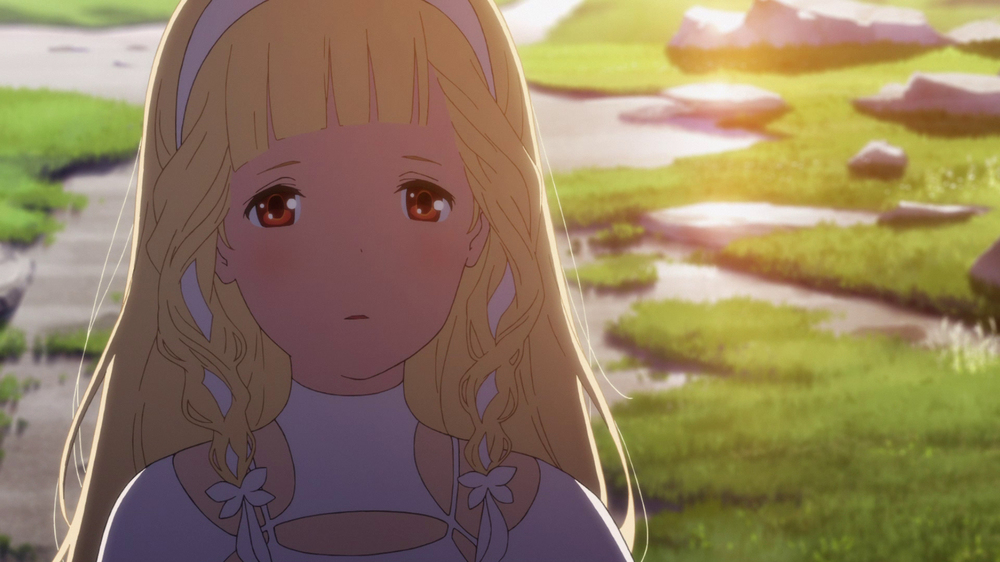
『さよならの朝に約束の花をかざろう』© PROJECT MAQUIA
ミルドレッドもマキアも“母の愛”という言葉でくくられそうに見えながら、それを否定するかのように“そうせざるを得ない”行動をとる。どちらも“母は強し”とざっくりまとめられそうな映画に見えつつも、2人の行動から浮かび上がってくるのは、ミルドレッドでありマキアというキャラクターの“本人の顔”なのだ。「母である私」が何かを語るのではなく「私が母である」という(当たり前の)事実を告げる映画といってもいい。母の愛がもしあるとしたら、そんな“私=エゴ”の先に待っているのだろう。
文:藤津亮太