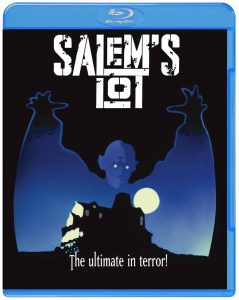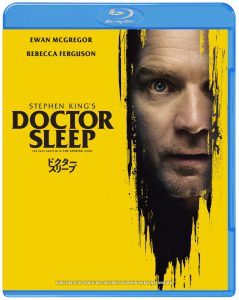スティーヴン・キングを考察 『シャイニング』『スタンド・バイ・ミー』『IT/イット』モダンホラーの帝王が綴るアメリカ神話
スティーヴン・キングが確立したホラー手法
「モダンホラーの帝王」と言われるスティーヴン・キング。彼の小説は映画、TVドラマ等々で、ほとんど映像化されていると言ってもいい。
キング作品の特徴としては、クラシックな題材を正面から見据え、「もし、それらが現代社会に現れたらどうなるのか? 社会や現代人はどんな反応をするだろう?」という疑問を突き詰めていく。文章も、単なる“ティッシュ”と書かずに“クリネックス”など商品名を挙げ、徹底的にディテールを積み重ねていき、より読者が具体的な光景を思い浮かべられるように、現代社会の描写にこだわっている。
He Who Walks Between the Rows. pic.twitter.com/NGyJjLA8Wu
— Stephen King (@StephenKing) August 27, 2021
現代の町に吸血鬼が現れるTV映画『死霊伝説』(1979年)としてトビー・フーパーが映像化した「呪われた町」では、吸血鬼の体を調べた医師が、現代医療の見地から見れば彼らは慢性の貧血症である、と診断する描写もあった。ホラー的モチーフのディティールを積み重ねてリアリティを生み出す手法は、彼が確立したと言ってもいいだろう。
『死霊伝説』デジタル配信中
ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
キング作品の恐怖“全部入り”な『IT/イット』シリーズ
また、キングの特色としては基本、自身が恐怖を感じるものを作品モチーフにしている。クローゼットからブギーマンが出てくるかもしれないのが怖くて、いまだに明かりを消して眠ることができないほどのキングは、
狂信的なファンが作家に危害を加えてきたら→『ミザリー』(1990年)
もし子供が死んだら→『ペット・セメタリー』(1989年)
狂犬病の犬が怖い→『クジョー』(1983年)
など、自分にとって多くの「怖いもの」を徹底的に見つめ、物語を生み出してきた(そして映画化されてきた)。その決定版として放たれ、映画化されたのが『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』(2017年)と『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』(2019年)である。なにせ相手の恐怖を餌にしているため、“犠牲者の恐れているものに変わる”という、まさにワイルドカード。今までのキング作品全部入り的な作品である。
『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』デジタル配信中
ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
© 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC. All rights reserved.
一時期までキングは、「小説は面白いが、映画版はちゃちかったりしてあまり面白くない」と言われていた時期もあるわけだが、これは主にブロックバスター的なハリウッド大作が盛んになっていた1980~90年代あたりに言われていたことで、ホラー映画不遇の時期でもあった。
『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
この説が今では余り言われないようになったのは、おそらくはCGなど、超常的な現象を見せるためのツールの進歩が大きかったのではないか。キングの描き出す世界観に映画界の技術が追いついた、ということかもしれない。
今ではキングは原作、映画版両方から入ることの出来る、「見てから読むか、読んでから見るか」、悩ましい作家であると言える。
『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』ダウンロード販売中、デジタルレンタル中
ブルーレイ 2,619円(税込) /DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
唯一否定した映画化『シャイニング』と『ドクター・スリープ』による雪解け
キング自身が筋金入りの映画マニアであり、映画などのホラー作品との出会いや、自作の映画化作品などについて語った映画研究本「死の舞踏」という著作すらある。その中で基本キングは自作の映画化作品に愛を捧げ、たとえチープな作品であったとしても、理解を示し応援している。ただ一本の作品をのぞいては。その作品が『シャイニング』(1980年)――皮肉なことに、キング映画化作品の中でも最も有名な映画の1本である。巨匠スタンリー・キューブリックによるホラー映画の金字塔であるが、まぁとにかくこれがキングのお気に召さなかった。
『シャイニング』
北米公開版<4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスター ブルーレイ>(2枚組)6,345円+税
ブルーレイ 2,381円+税/DVD 1,429円+税
ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
© 1980 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
キングの原作では、主人公ジャックがだんだん幽霊に蝕まれ、狂気に陥っていく、という物語だった。しかし、キューブリックはキングの脚本を拒否し、幽霊話というよりは閉鎖空間である冬山のホテルの中で(幽霊と、そしてジャックに)追いつめられていく登場人物、というサイコホラー的な側面に着眼した。登場する少年ダニーの持つ超能力“シャイニング”も、映画版ではダニーの精神的な病のようにすら見える。
『シャイニング』© 1980 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
アルコール中毒、執筆のスランプと家族へのいらだち、そんな私的な感情や体験をそそぎ込んだ作品を、全く異なる物語にされたキングの怒りはいかばかりか。映画版のビジュアルは褒めたが、表面だけで中身がない「エンジンのない高級車」と酷評し、「この映画がなぜ怖いと言われるのか判らない」「『シャイニング』以外のキューブリック作品はすべて好き」とケチョンケチョン。
『シャイニング』© 1980 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
しかし皮肉なことに、キューブリックの映像美と恐怖表現が混じり合い、『シャイニング』はホラーの名作と言われるほどになってしまった。迷路やタイプライターのシーン、2人の姉妹、エレベータの血の濁流など、映画版で有名なシーンはすべて原作にはない。同作はスピルバーグの『レディ・プレイヤー1』(2018年)にも登場するくらい、すっかりホラー映画のアイコン、カルト映画化したと言える。
https://www.instagram.com/p/B2mbNYaFfMt/
もちろんキングは面白いわけがない。その後も映画版を否定し続け、自分自身でTVシリーズ『シャイニング』(1997年)を監督し、30年以上経ってから続編小説を執筆するほどだった。
その続編の映画化が『ドクター・スリープ』(2019年)だが、原作はもちろん小説版の続編である。しかし一般のイメージはキューブリックの映画版こそ『シャイニング』だと思われているため、映画版の生み出したイメージも無駄にできない。しかもオチが小説と映画とでは全く異なる……。幾重にも難題山積した状態を、監督マイク・フラナガンがどうまとめたのか? そのあたりも要注目である。
ちなみにキングは『ドクター・スリープ』を観て初めて、キューブリックの『シャイニング』に多大な感謝をした。「自分の作品の映像化にこだわりすぎていた」と。『ドクター・スリープ』はキングの心を溶かした作品とも言える。
『ドクター・スリープ』デジタル配信中
ブルーレイ 2,619円(税込)/DVD 1,572円(税込)
発売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント
販売元:NBC ユニバーサル・エンターテイメント
Doctor Sleep © 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.
アメリカ文学の要素を「モダン」に発展『スタンド・バイ・ミー』
ホラー以外の作品も数多く執筆しているキング。当然のようにそれらの作品も映像化された。『ドリームキャッチャー』(2003年)や『ダークタワー』(2017年)などのSFやファンタジーはもちろん、『ショーシャンクの空に』(1994年)や『アトランティスのこころ』(2001年)など、キングらしい超常現象も含む一般小説のテイストを持つ作品も多くなっていく。
ホラーに興味がなくとも、ジャンルや世代を越えて観られているキング原作映画は多々あるが、その最初は間違いなく『スタンド・バイ・ミー』(1986年)だろう。少年たちの友情や疎外感を、死体を探しに行くという一夏の冒険の中で描いた本作は、あまりに実体験に即しすぎていたため、鑑賞後キングは号泣し、15分も席を立てなかったそうである。
『スタンド・バイ・ミー』Blu-ray
価格:¥2,381+税
発売・販売元:ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
子供の頃の体験などをヴィヴィッドに描き出す、青春小説の側面が強い作品が多いのもキングの特色だ。それだけでなく、子供→大人の変化も重要なモチーフであり、大人になることは自由なことばかりでなく、子供の時の純粋さを失い、守らなくてはならないものも増え、よりハンデがついてしまう、といったあたりもよく描かれる。この構造は『シャイニング』と『ドクター・スリープ』、『IT/イット』前後編の間にも成立する要素だ。
『スタンド・バイ・ミー』©1986 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. ALL RIGHTS RESERVED.
当然、「トム・ソーヤーの冒険」などのアメリカ少年文学的な要素の影響は濃厚だし、『スタンド・バイ・ミー』の作中でキャンプのたき火を囲んで語られる、いじめられっ子の壮絶な復讐を描いた「パイ大食い競争」(個人的にはこの逸話がキング作品映像化の最高峰だと思っている)や、刑務所でのホラ話的な物語がやがて感動を呼ぶ『ショーシャンクの空に』や『グリーンマイル』(1999年)など、口伝から発展したアメリカ大衆、説話文学の影響を見ることもでき、キングはホラーだけに留まらず、様々なアメリカ文学の要素を「モダン」に発展させている気もする。
アメリカ独自の「神話」を生み出し続けるキング
これはアメコミにも言えることであるが、歴史の浅い国であるアメリカには、宗教はあっても神話が存在しないためか、そういったものを求める気持ちがある。そこに様々な伝承、都市伝説やフォークロア、子供の恐怖のようなものを現世に蘇らせ、アメリカ独自の「神話」を形作っているのがキングであるとも言える。
— Stephen King (@StephenKing) March 6, 2020
超人的ヒーローが登場するアメコミが神の側から描かれた神話だとすれば、キングはその世界をより一般人の立場から編み直した神話を作り続け、映画化作品も含めて現代アメリカ文化を形作っている、ということだとも言えるだろう。
9月21日に誕生日を迎え、2021年で74才になるキング。作家としてもまだまだ活動盛んだが、ジミヘンやジャニスなど、死んだはずのアーティストが生き続ける町があった、という短編「いかしたバンドのいる街で」、最後の一人になるまで続く地獄版「夜のピクニック」な「死のロングウォーク」など、映画化されていない作品もまだあるので、それらの映像化が楽しみである。
— Stephen King (@StephenKing) September 21, 2019
文:多田遠志
『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』、『シャイニング』、『ドクター・スリープ』、『スタンド・バイ・ミー』はCS映画専門チャンネル ムービープラスで2021年9~10月放送
https://www.youtube.com/watch?v=IxylidSRed4