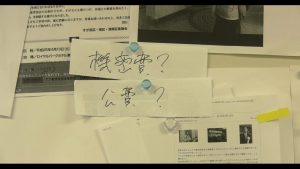「若い人が政治に興味を持たないのは我々の責任」
「企画・製作・エグゼクティブプロデューサー 河村光庸」――邦画ファンにとって、このクレジットには見覚えがあるはず。河村氏は『新聞記者』と『i-新聞記者ドキュメント-』(ともに2019年)で新藤兼人賞ドキュメンタリー賞を受賞。ここ2年で公開された作品だけでも『MOTHER マザー』(2020年)、『ヤクザと家族』(2021年)と国内賞レースに必ずかかる、数多くの話題作を手掛けてきた。
2021年7月30日(金)より公開中の『パンケーキを毒見する』は、就任直後の番記者とのパンケーキ食事会で注目された現政権を徹底解剖する“政治バラエティ映画”だ。日本ではあまり制作されない政治ドキュメンタリーをミニシアターではなく、シネコンで公開する意義を河村氏に聞いた。

河村光庸プロデューサー
「このテーマに“出会って”しまった」
―『新聞記者』『i-新聞記者ドキュメント-』で批判を続けてこられた対象に対して、いよいよ『パンケーキを毒見する』で本丸に斬り込まれたなという感じがしたんですが。
いや、なにも意識していないです。斬り込んだということになるのかもしれませんが、『新聞記者』に関してはドキュメンタリーとドラマ(劇映画)をやりたいと思っていたんです。同じテーマで二本同時にやるのは世界的にもないでしょうし。でもそれは無理だということになって、まずドラマをやろうと。並行してドキュメンタリーの準備をしたのは相乗効果を狙ったところもあったんですが、実際にはうまくいかなかった。
『パンケーキ~』は、まず新型コロナウイルスの問題がありました。ドラマは多くの人が集まって撮影するので、たとえば俳優さんが感染したりすると、それだけで撮影が伸びたりするリスクがある。じつは、それで何本か仕掛けていた企画が飛んでしまったんです。
そこで、じゃあドキュメンタリーを撮れるじゃないか、よしこれだ! と。もちろん菅政権というテーマに“出会ってしまった”部分もあります。
―このテーマが浮上したとして、それを見て見ないふりをする人も多くいると思います。でも、それをやらなければとお思いになったのは……強い信念があった?
強い信念というか(笑)、やっていいんじゃないかと思うんです。

『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
「多くの“有権者”に観てもらうために大きな劇場で公開したい」
―その“やっていい”という思いについてなんですけれども、これまで政治的な映画って、ほとんどポレポレ東中野やユーロスペースでしか公開されず、作る側にも固定観念があったと思います。ですが『新聞記者』はイオンシネマで、『パンケーキを毒見する』は新宿ピカデリーで公開されます。どうやって大劇場を押さえることが可能になったのでしょうか。
やはり一定のお客様に観てもらうだけでなく、多くの劇場にたくさんの人を集めることが大事ですよね。そもそも映画というのは、そういうものだと思います。しかも、お金を払って観に来てくださるわけですから。そういう障壁を乗り越えて、大きな劇場で観る映画を作らなければならない。そのためには一般向けにするべきだし、いわゆる“単館が好きな人が必ず観る”という映画ではなく、たとえば18歳から30歳の“有権者”に観てもらいたいと。
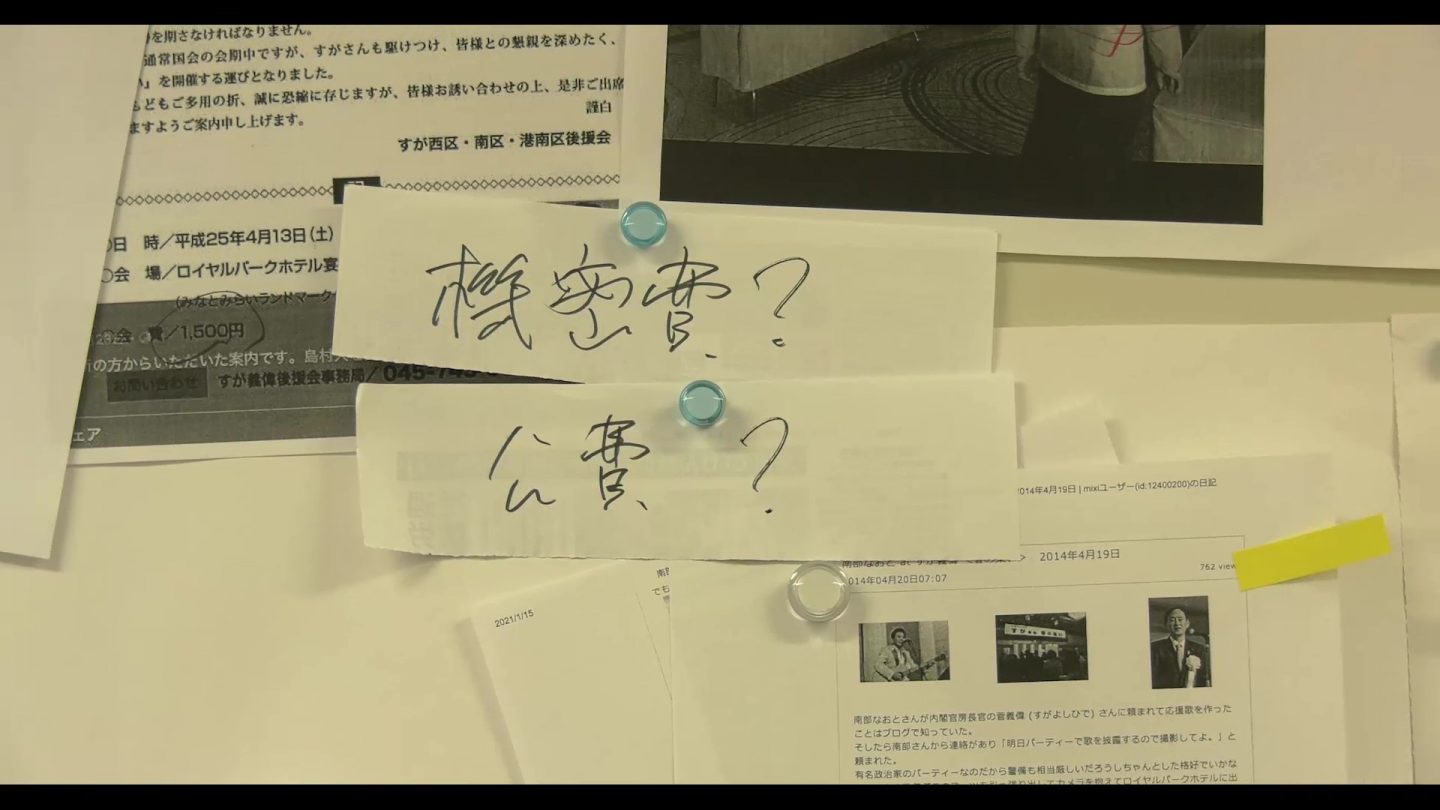
『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
今回は特に若者に観てほしいと思い、日大の芸術学部の学生たちに観てもらったんですが、後でアンケートを取ったら、ほとんど全員が政治に興味がなかった。映画を作ろうと思って学校に入っている人たちが、政治に興味がない。
しかし、この映画を観て「投票しようと思った」、「すごくよかった」、「今まで、どこにどう投票したらいいかわからなかったが、そういったことに指針を与えてくれた」という声が集まった。彼らにとっては右翼も左翼も、政党もないんです。

『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
そのとき、ある学生に「河村さんにとって“若者”とは何ですか?」と、すごく鋭い質問をされて、ドキッとした。思わず「ごめんね」と言ってしまったんです。“コロナは若者が蔓延させる”と報道するなど、若者という言葉で一括りにすることに以前から抵抗はあったんですが、そうしたひとつの概念で、私も彼らを一括りにしていた。それは若い世代への差別になってしまうから、少なくとも「何歳から何歳です」と具体的に答えるべきですよね。

『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
「大ヒットした『鬼滅』や『エヴァ』は逆に映画館を危機に陥れた」
ひとつの教育の時代が変わり、社会が変わって、新自由主義社会、競争社会に生まれて育ってきた世代が社会に出てくる。若い人に政治に興味を持たせないでやってきたのは、我々の責任です。とくにマスコミ、そしてやはり劣化した、言葉を否定するような政治家たちの責任なんじゃないか。
それをしっかり観てほしいと思っているので、間口を広げるべきだろうと。そして映画館の方に理解を求めて、うちがどんな規模の映画を作ってもシネコンでやるべきだろうと、映画館側と話をしました。

『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
シネコンはご承知のように、アニメに席巻されています。よく、コロナ禍で『鬼滅の刃』(※『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』[2020年])が映画業界を救ったと言われますが、私は実写映画に関わる人たちや小さい映画を、あのアニメ映画が排除したと思っています。
学生たちに、「じつは『鬼滅の刃』や『エヴァンゲリオン』は、ある一定の映画館と映画会社しか儲からなかった。小さな映画を作っている人たちや実写の人たちは、みんなアニメ映画のおかげで排除されたんだから、逆に映画界を危機に陥れたことになるんだ」という話をすると、皆びっくりするわけです。もちろん映画としては否定しないし、娯楽映画として素晴らしいと思うのですが、製作者としてはやっぱり辛かった。そうした映画の多様性についても話をしながら、シネコンで公開することになったんです。

『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
―大手制作会社がアニメや必ず当たる大御所の作品に頼りきっている中で、まったく違う作品を制作されているからこそ、河村さんの存在感が引き立つのではないでしょうか。
ひと昔前であれば、いろんな人にもっとチャンスがあった。こういう時代だから“存在感”なんて言われるけれど、それだけ社会が一元化して言葉が劣化しているということでもある。政治の劣化が激しいし、行政、マスコミも含めてどんどん劣化していく。そんな時代だから目立っているだけだと、私自身は思っています。

『パンケーキを毒見する』©2021『パンケーキを毒見する』製作委員会
取材・文:遠藤京子
『パンケーキを毒見する』は2021年7月30日(金)より新宿ピカデリーほか全国公開中
『新聞記者』は各配信サイトにて配信中