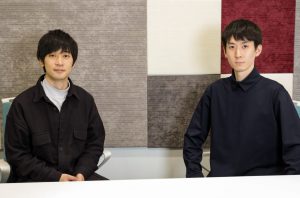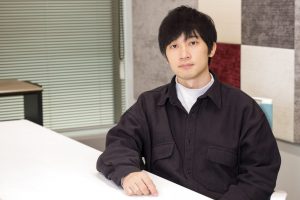「コンビニに行くような感覚で挑戦的なオーディオ作品にバッタリ出くわしてもらいたい」
プロのナレーターが朗読した本をアプリで聴けるサービスAmazon Audibleから、日本初のオリジナルスクリプト作品として、映画監督・堤幸彦氏らが手掛ける『アレク氏 2120』が登場。山寺宏一や梶裕貴、三石琴乃、窪塚洋介、伊藤歩など日本を代表する声優/俳優陣が集結した「聴く映画」こと『アレク氏 2120』は、映画的な音響効果を緻密に練り上げて製作された、サウンドノベルとは一線を画す新たなオーディオコンテンツだ。
『アレク氏2120』
この『アレク氏 2120』は、Amazon Audibleが持つ可能性を今後どのように広げていくのか? 本作の制作に携わった<NEOTERIC>のPodcastプロデューサー・白井太郎氏と、氏が敬愛するミュージシャン、Base Ball Bearの小出祐介氏による対談インタビューの【後編】をお届けする。
オーディオコンテンツにおける劇伴
―小出さん主宰のマテリアルクラブは映画『ゴーストマスター』(2019年)に主題歌を楽曲提供されていますが、映画音楽をやってみたいという気持ちはありますか?
小出:主題歌はできても、劇伴となると思考回路が違うと思います。友人の世武裕子さんから劇伴制作の話を聞いたりしますが、主題歌の制作とは制作過程も、求められることも違うんですね。自分にはできないことだと思っています。
白井:劇伴は、劇伴を作るミュージシャンとは別に音楽プロデューサーがついて、編集でミックス作業をしながら、Pro Toolsなどで映像に合わせてその場で音楽を編集するんですね。ある場面はリズムだけにしたりなど、その場その場での細かな指示があります。プライオリティとしては本編に合わせるという部分が優先にはなってしまうので、主題歌などの楽曲提供とは違うところがありますよね。
小出祐介
―そうした劇伴を今後、オーディオコンテンツでもやっていくのでしょうか?
白井:今回製作しながら思ったのは、映画の劇伴とオーディオドラマの劇伴がまったく違うということです。映画の劇伴は登場人物の心情に寄り添って、映像の補足説明的な役割がメインです。また、とてもカオスなシーンに敢えて真逆のクラシックなどを流して、映像を際立たせるメソッドなどもありますよね。視覚からの情報と聴覚からの情報という、2つのレイヤーで脳内で処理されるから、そのような技法が成り立ちます。ですがオーディオファーストのドラマでは、物語も音楽も聴覚からの情報のみで、1つのレイヤーとして脳内で処理されてしまいます。つまり、音声よりも音楽が立って聴こえてしまう場合があるんです。
小出:音楽が情報として強いということですよね?
白井:そうなんです。音楽の情報量ってとても多いんだな、ということに今回気づきました。耳が台詞よりも音楽のメロディのほうへ引き寄せられてしまうんです。台詞のテンポを出すためにリズムだけにしたり、音楽のボリュームを下げるような調整は本作でも多々ありました。
小出:曲にドラマが乗っているような感覚ですね。
白井:おっしゃる通りで、曲に誰かが声を乗せているような。それがすごく難しくて、今回思ったのは、劇伴(音楽)のあり方というのもオーディオファーストのドラマでは一つの課題である、ということですね。映画の劇伴の感覚で作ると、音楽が立ってしまい、オーディオコンテンツとしてうまく表現できないということを感じました。堤監督はとても音楽や劇伴に対する造詣が深く、また本作の製作総指揮の宮川さんも、そのようなバランスに対する耳の感覚が極めて鋭い方です。お二人の指示がとても的確で、その導きにより、音楽とセリフのシンクロ率を高めていくことができました。
左:白井太郎 右:小出祐介
小出:撮影監督と一緒に映像的な部分を開発していくように、オーディオコンテンツで劇伴をやるとなると、音楽家と一緒に企画段階から並走していかないと難しいんでしょうね。
白井:そこがちゃんとシンクロしたら、すごく面白いものになると思うんです。本作にもテーマ曲はありますが、いわゆる歌なしのインストです。歌が入ってしまうと、それが立ってしまうので。次作では、エンドロールに主題歌を乗せたいという気持ちがありますね。ただ、音のドラマに乗せる主題歌は通常の映画とは違いますし、手法を変えなくてはとは思っていて。通常の映画のような主題歌だと、その瞬間だけ単純に音楽になってしまうんです。
小出:正直、ただ音楽を聴いているだけになってしまいそうですよね(笑)。本編はずっと耳で聴く映画的感覚でいて、エンディングで曲が流れてもデータの最後に曲がまるまる入っているだけ、という感じになってしまう。
白井:そういった問題点を加味して、小出さんに楽曲を作っていただいたら可能性があるのかなと思うんですが。
小出:エンドロールの中でナレーションと役者さんたちの掛け合いがあることを考えると、通常の楽曲では確かに情報量が多いので、歌の情報量を引っ込めることで、エンディングがドラマの延長として聴こえるようにはなるのかなと思います。歌が多いと、台詞に被って歌がうるさく聴こえてしまうか、歌自体を聴いてしまって台詞がうるさいか、だと思うんです。例えば「ルパン三世」のテーマのような曲が流れている中で、ナレーションが乗せられるというイメージ。台詞の邪魔はしなさそうですよね。「マルサの女」はどうでしょうか。あれもテーマが耳に残るので、歌がなくてもテーマソングとして成り立つと思います。
オーディオコンテンツの“隙間”を模索する次回作へ
白井:Audibleのようなオーディオ作品では、映画とは違ってひとつひとつの台詞が立っていても成り立ちます。映像だと誰かが喋っている映像があって、リリカルな一言が立っている表現があっても、“これは台詞として普段、人が言わないだろう”という違和感を感じることが多々あります。しかしオーディオでは画がないことによって、そのあたりの違和感がなくなり、言葉の表現が強くてもオーディエンスが引かないんですよね。
ハリウッドの映画製作だと、プロットを書く人、ストーリーエディターがいて、台詞だけを書く人もいます。日本だとそれを脚本家がすべて一人で執筆しますが、Audibleでは開発段階で、そうしたハリウッド式の製作方式を採用することができると思っています。映画の準備段階では、シナリオを制作しながらロケハンを行い、美術や衣装を決めたりなど無数の作業に追われるわけですが、オーディオファーストでは物語の開発に集中できる場が提供できます。逆に、そういったチャレンジングなことをやっていかないと、映像や既存のオーディオコンテンツとの大きな差別化は図れないと思っています。
小出:確かに日本映画の脚本開発は、海外とは体制がまったく違いますよね。そうした充実した脚本開発がAudibleのコンテンツでできるのなら、素晴らしい試みかもしれませんね。
白井:黒澤明監督も、4、5人の脚本家と旅館に泊まって共同作業で脚本を練り上げていたわけですから。かつてはそういうことをやっていたのに、今の日本映画ではそれができないという。次の作品では、オーディオならばそうした製作が可能なんだ、ということを実践で示していきたいです。そうして、「音だけ」というステージでは日本も海外コンテンツと互角に戦えるんだと思ってもらえる作品を作りあげたいですね。
白井太郎
―アメリカのAmazon Audibleでは、すでに多くのオリジナル作品があるんですよね?
白井:そうなんです。日本ではAudibleがリーディングカンパニーとなり業界を引っ張っていますが、海外ではAudibleはもちろん、インディペンデントのPodcast会社も多くあります。海外のオーディオ作品では、映像化する前のパイロット盤をオーディオファーストで作ることも多くなっていて、すると脚本よりも物語の全体像が掴め、映像化する際のイメージがし易くなるわけですね。かつ、パイロット盤自体がひとつのオーディオコンテンツにもなり、それを二次利用で映像化することもできる。とても理にかなった構造ですよね。
小出:このオーディオコンテンツから逆に映画化される、という企画も生まれてくるのでしょうか?
白井:Audible『アレク氏2120』に関しても、映像化の可能性は十分にあると思っています。私としては、一度オーディオという媒体で完結している作品なので少し複雑な気持ちもありますが、とはいえ詩集も新聞コラムも、音楽でさえも無数の原作が映像化されるこの時代に、オーディオファーストの本作が原作としての魅力を認められることはとても嬉しいですね。
『アレク氏2120』
小出:新しいメディアミックスの可能性になる気がしますね。これからオーディオでの文化が日本でも広まっていったら、今度はオーディオドラマをディグる人たちも出てきたりして。
白井:本作によってひとつ土壌ができることで、おっしゃるようにディグる人たちが出てきて、「オーディオって可能性があるな」と多くのクリエイターたちの気付きのきっかけになってくれれば、これ以上の喜びはないですね。ところで、小出さんは、小説を書いたり、物語を作るという発想になったことはありませんか?
小出:これも時々聞かれることなんですが、まったくないんです。小説を読んで、これなら自分でも書けるなとか、こういうものを書いてみたいと思ったこともないです。やはり“作り”が違うんですよね。友人に朝井リョウという小説家がいますが、朝井くんの執筆の話を聞いていると、テーマ性や考え方にはすごく共感するものの、表現のプロセスも異なりますし、アウトプットとしての着地が全く違うので感心します。
小説は、説明にある程度の量が必要だったりしますよね。一方、歌詞はメロディーに合わせて作りますから、文章として見た時にかなり隙間があります。歌った時の言葉の音というか、“口当たり”を重視することも多いですし、説明をダラダラ歌っても仕方がないので、比喩でまとめることも多く、聞き手の想像力に任せることも大切です。そのぶん、解釈が開かれているというか。当然、小説にもそうした部分はあると思うんですが、基本的にルールの違う表現だと捉えています。
小出祐介
―その意味では、オーディオのスクリプトは映画と小説の中間くらいなんでしょうか?
白井:今回は映画のスクリプトの形式と、ほとんど変わらず書いていただいています。ト書きもそのまま書いていますし、特別、小説的な要素が入っているわけでもないですね。ト書きがないとスタッフも場面を具体的にイメージできないですし、役者さんもどう読んでいいのかわかりません。映像化のためのト書きではなく、ひとつの指針としてのト書きがあります。
小出さんのお話を伺って、逆に隙間のある作品、オーディオコンテンツでは省略すべきところは省略できるので、聴く物語だと曖昧さが許される。視覚で具体的に見えているわけでないので、聴き手はそのままを受容してくれる部分が多いんです。本作は日本初のオリジナル作品ということもあり、オーディエンスに丁寧に物語を伝えようと、映画のように理詰めの作業に重きを置いていたところもあります。本作は、物語に置いていかれることなく楽しんでいただけると思っています。
ですが、これからの作品では、省略による“隙間の曖昧さ”を追求してみたいですね。例えば脚本家数人で物語を作った上で、言葉のブラッシュアップを小出さんにやっていただいて詩的な隙間を持つニュアンスを出しながら、音楽もやっていただくという。そうしたチャレンジングなものを、いつかご一緒できたらと心から思っています。
小出:そうしたお手伝いはできる気がしますね。コンテンツというか、ひとつの表現形体としてAudibleは面白いと思います。Amazonは日常的にコンビニに行くような感覚で覗いている人が多いと思うので、挑戦的なオーディオ作品にバッタリ出くわしてもらいたいですね。
左:白井太郎 右:小出祐介
取材・文:加賀谷健
小出祐介:
2001年に結成されたロックバンドBase Ball Bearのボーカル・ギターを担当。これまで2度にわたり、日本武道館でのワンマン公演を成功させる。また、音楽プロジェクト・マテリアルクラブの主宰も務める。
白井太郎:Twitter:@pdd_Taro
1995年生まれ。“NEOTERIC Co. Ltd.”所属のPodcastプロデューサー。企画・プロデュース作品である堤幸彦監督『アレク氏 2120』(Amazon Audible)など、Podcast制作に多く携わる。